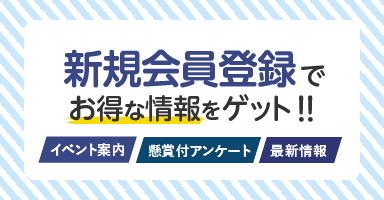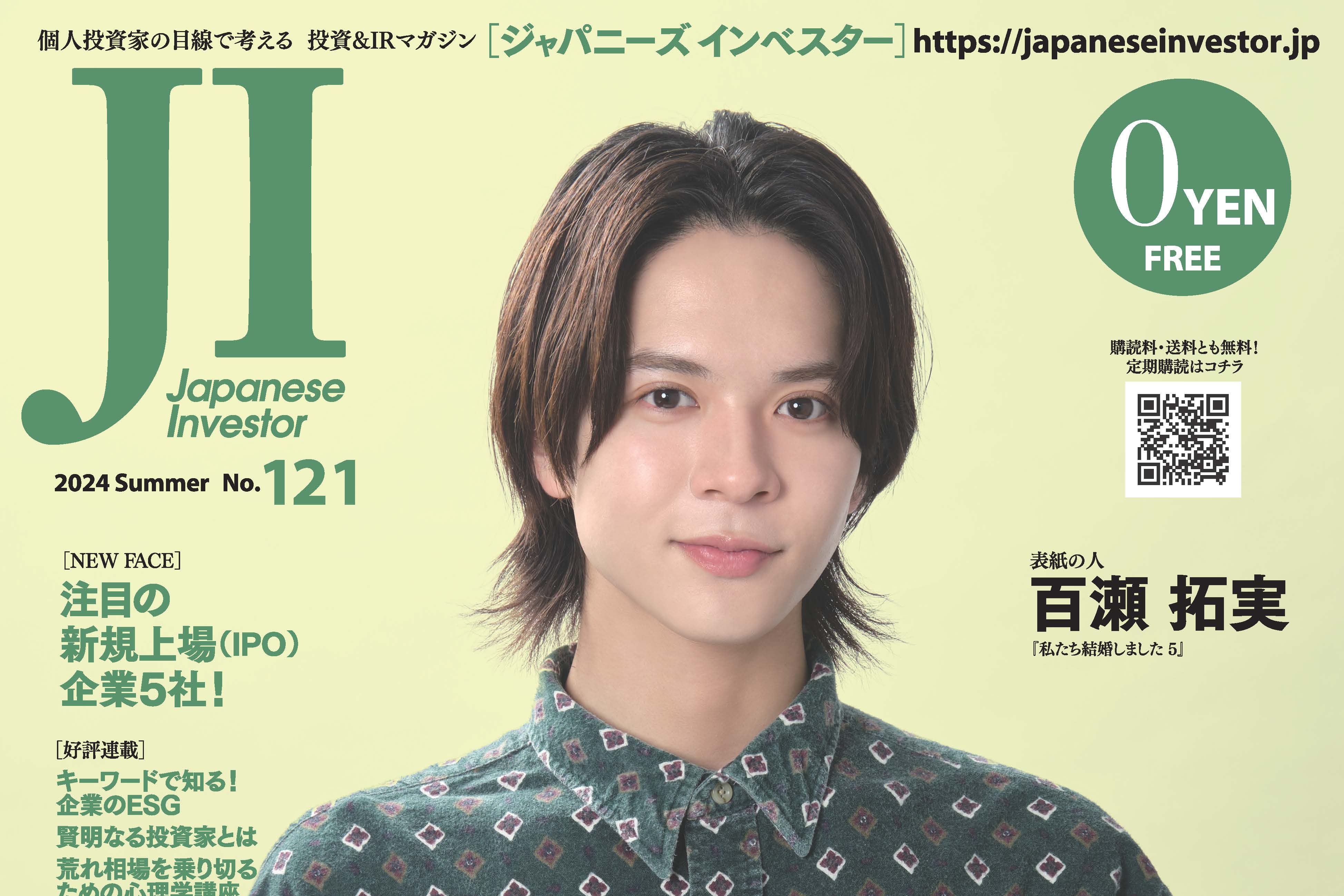啓蒙する
文/木田 知廣
※この記事は2023年7月25日発行のジャパニーズインベスター118号に掲載されたものです。
最近の若者は…
最近の若者は“できた人”が多いってご存じでしょうか。たとえば大学生。授業が朝の一限目からあっても、遅れることなくちゃんと出席するそうです。筆者が学生だった頃は「自主休講」なんて当たり前。ときには自分の代わりに友人に出席の返事をしてもらう「代返」でなんとか出席をクリアして単位だけはもらおうなんてしていましたから、雲泥の差ですね。ところが、当の学生自身は「当たり前の事をしている」感覚なのだとか。要するに、“決められた事”に従うのに違和感がないそうなのです。
これを証明した心理学の実験がアメリカで行われました。対象は7〜9歳の子供ですが、ちょっと難しめのパズルに挑戦してもらうのです。その際、グループを3つに分けて、最初のグループにはどのパズルに取り組むかを自分で決めさせます。一方、二つ目のグループには、実験の主催者が割り振ります。そして、三つ目のグループには、「これは、君のお母さんが選んでくれた問題だよ」と告げるのです。実際のところは母親の関与はないのですが、少なくとも子供の方はそう信じて取り組みます。
パズルはいくつもあるので制限時間内には終わりません。すると、休憩時間にもそのままパズルに取り組んだ子供が現れて、その数が最も多かったのは、ご想像の通り三つ目のグループ。おそらく、お母さんが選んだ問題は“決められた事”なんだから、それに従わなければと思ったのでしょう。
なお厳密には、このように思ったのはアジア系の子供だけだったそうです。ヨーロッパ系の子供は最初のグループ、つまり問題を自分で選んだ子供の方が休憩時間になってもパズルに取り組み続けたそうで、これはこれで示唆的です。
ただ、いずれにしても不思議。なぜ人間にはそのように“決められた事”に従おうという習性があるのでしょうか?この謎を解く鍵が本連載のバックボーン、「進化心理学」です。
群れを超えて協力する
「進化」というキーワードでピンと来た人もいると思いますが、ダーウィンが提唱した動物の進化の考え方を心にも当てはめたのが進化心理学です。つまり、人間の心も環境に合わせて適応していくとの考え方です。逆に言うと、適応できないと「淘汰」されてしまうことになりますね。
では、時間を逆回しして人類誕生の100万年前に戻って、淘汰されずに生き延びるためにはどんな心のはたらきが必要かを考えてみましょう。野生の猛獣と比べて牙もなければ爪もない、か弱い肉体を持つ人類が生き延びるためには、「群れ」で生活する事が必須でした。ただ、実は群れのメンバーの数は「上限」があるそうです。その数、ズバリ150人。学生時代だと30人のクラスが5クラスで1学年150人ぐらい。だいたい全員の名前と顔が一致する感覚が分かってもらえるでしょうか。
ところが、この数を超えると同じ群れにいても「あなた誰?」と言うことが起こるのです。たとえば急成長するベンチャー企業で働いた経験がある方ならばイメージがわくでしょう。社員の数が150人くらいまでだと、誰が何をやっているかが分かります。ですが、150人の規模を超えた途端に、「あれ?こんな人ウチの組織にいたかなぁ」と「よそ者」に感じてしまう状態です。

現代ならばネットやメールで交流できますが、そんな便利なものがなかった太古の時代、メンバーの数が150人を超えた群れは自然と分かれて、別の群れを形成するようになったのです。ところが、このように上限が決まっていることは、人類が文明を築くときには大きな妨げになりました。たとえば文明発祥の地の一つ、エジプトを考えてみて欲しいのですが、ピラミッドを建てるには150人以上の人間が必要ですよね。群れが150人ずつに分かれていたら、協力し合うのが難しくて大きな成果を上げることはできません。
そこで出てきたのが宗教。なんらかの「大いなるもの」を信じることで、親族やご近所さんを超えて150人以上が一致団結して協力する体制ができるのです。なので、古代文明と宗教はセットになっていて、ファラオと呼ばれるエジプトの王様は神様の使いを兼ねていました。このように発展してきた人類ですから、神の使いである王様によって“決められた事”に従う気持ちが根強く形成されています。冒頭の学生の話に戻ると、ルールに従って朝早くから授業に出席する最近の学生の方が進化心理学的にはよっぽど理にかなっているのです。
啓蒙上手な会社
では、今回の発見を投資に活かす方法を考えてみましょう。それが、消費者を啓蒙するのが上手な会社。つまり、ライフスタイルを「こうあるべきだ」と演出して、まるでそれをやるのが当たり前、つまり“決められた事”のように訴えるのが上手な会社は今後業績を伸ばしていきそうです。
たとえば、消臭剤を売っている会社はその典型例と筆者は思っています。昔、それこそ筆者が若かりし頃は、消臭剤と言えばトイレに置いてあるきつい臭いのものがメインでした。でも、ふと気がつけば今の私たちの周りには、置くだけタイプ、ワンプッシュするタイプ、スプレーするタイプとさまざまな消臭剤にあふれています。まるでそれは、「服も絨毯も布団だって、スプレーで臭いを消すのが当たり前」と“決められた事”を演出しているように見えます。消費者が思わず製品を買ってしまうのもうなずけます。
他の業界でも探してみて、このような「あるべきライフスタイルを打ち出して、消費者を啓蒙するのが上手な会社」というのが見つかったら、その会社の株は「買い」かもしれません。
参考文献
金間大介著『先生、どうか皆の前でほめないで下さい:いい子症候群の若者たち』東洋経済新報社、2022年。
【著者プロフィール】
米マサチューセッツ大学のMBA課程で教鞭を執る、ビジネス教育のプロフェッショナル。専門分野の「組織行動論」を活かした企業分析を投資にも活かしている。
ブログ(https://kida.ofsji.org/)でも情報を発信するほか、ツイッター(@kidatomohiro)では、「MBAの心理学」と題して投資や仕事に役立つ心理学の発見を紹介している。