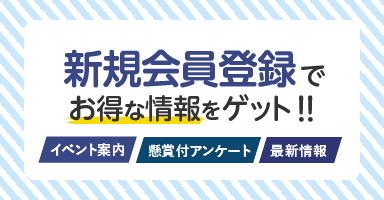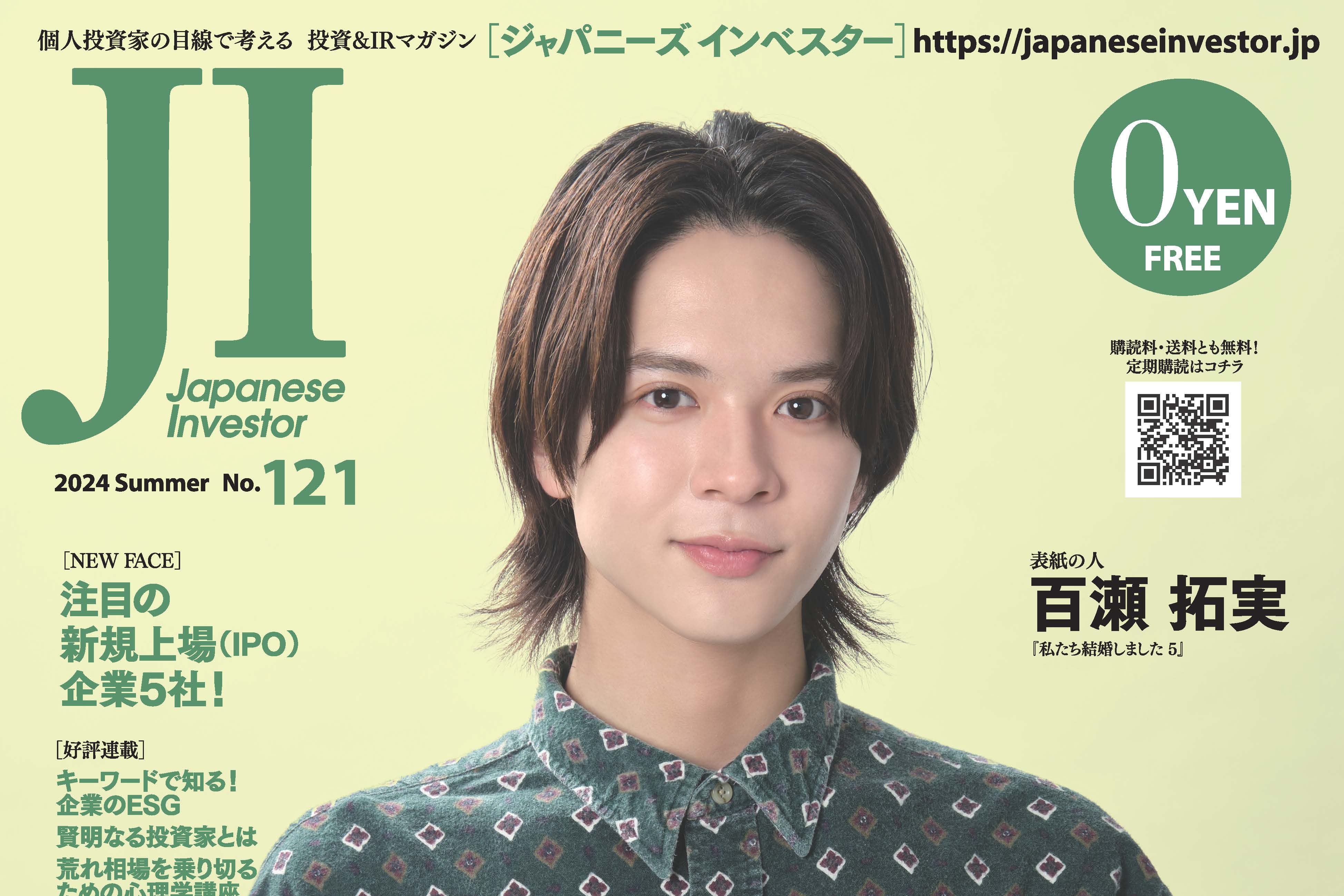統合報告書

文/片桐 さつき
これまで「企業のESG」では、企業のサステナビリティ情報をどのように投資判断に加味できるのかをキーワードを紐解く形でお伝えしてきた。今回はその情報源である「統合報告書」の読み方について、改めてお伝えしていこう。そもそも「統合報告書」とは何か。四角四面に言えば財務情報と非財務情報を統合させた報告書、と解説できるが、例えて言えば「大海原を旅する企業という船の航海図」である。
大海原にある危険領域を把握し、誰よりも速く且つ着実に目的地にたどり着くために海路を決め、そのために積載するエンジンなどをコントロールし、そして船を進める。時には危険領域を通過することで他の船に差をつけ、時には積荷の変化に合わせて古くなったエンジンを積み替えることもあるだろう。統合報告書には、企業がどんなリスクを認識していて、どんな海路を選択し、どこを目指しているのか、そういった過去・現在・未来に亘る企業の物語が読み取れる要素が満載されている。
当研究所の調査によると、2022年12月末時点で800社以上の企業が統合報告書を発行しているが、皆様の投資先が統合報告書を発行しているか否かは、投資先企業のホームページで確認できる。サステナビリティサイトやIRサイトにおいて統合報告書のPDFを掲載している場合が多いので、投資先の航海図をダウンロードして是非手元に置いていただきたい。
まず読んでいただきたいのはトップ(CEO)メッセージだ。投資家をはじめとする多くのステークホルダーにとって、統合報告書におけるトップメッセージは舵取りをする船長の思考が把握できる最も重要なコンテンツと言える。年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、統合報告書のトップメッセージに求める要素のひとつとして「長期的な視点に立った会社の方向性、課題認識、経営理念、パーパス、それらに基づく長期ビジョンと持続的成長戦略について社長の熱意が伝わるメッセージ、目標達成に向けた強い意思」と公表している。これが皆様の投資先企業の統合報告書のトップメッセージにおいて表現されていれば、その航海に期待して投資を続けられるのではないだろうか。中には、どこの企業のトップメッセージに差し替えても分からないような総花的なメッセージになっている場合もある。残念だが、そうした企業の航海は信用できない、ということになろう。
トップメッセージで航海の全体像を把握した後は、指示した海路のエビデンスが統合報告書内で記載されているのかを読み解いていっていただくと良いだろう。もし財務担当役員(CFO)メッセージがあれば特にじっくりと目を通していただきたい。足元の業績解説だけではなく、事業における投資計画や効率的な資本配分など、社長が描いている持続的成長戦略を成し遂げるための、お財布のやりくりがロジカルに記載されているだろうか。また、中期経営計画を記載している企業も多いが、過去中計の振り返りや課題認識はしっかり記載されているだろうか。これから進もうとしている海路の信頼性は、過去の軌跡から得られることもあるため要チェックだ。
残念ながら、統合報告書というレポート名であるのにもかかわらず、サステナビリティ情報が中心で目的地に到着するまでのお財布のやりくりが読み取れないレポートも存在する。まずは皆様の投資先企業がどのようなレポートを作成しているのか把握していただきたい。もし投資家にとって有用ではない、もしくはレポートすら存在していない場合は、投資家にとって意義のある航海図を公表するよう皆様の声を投資先企業に届けていただければと思う。
※この記事は2023年7月25日発行のジャパニーズ インベスター118号に掲載されたものです。
片桐 さつき
㈱宝印刷D&IR研究所 取締役
ESG/統合報告研究室 室長
宝印刷㈱において制度開示書類に関する知見を習得後、企業のIR・CSR支援業務を担う。その後ESG/統合報告研究室を立ち上げ、現在は講演及び執筆の他、統合思考を軸としたコーポレートコミュニケーション全般にわたるコンサルティング等を行っている。