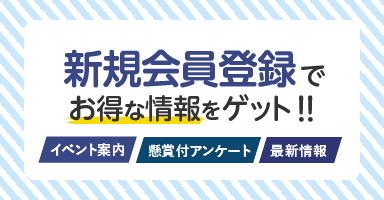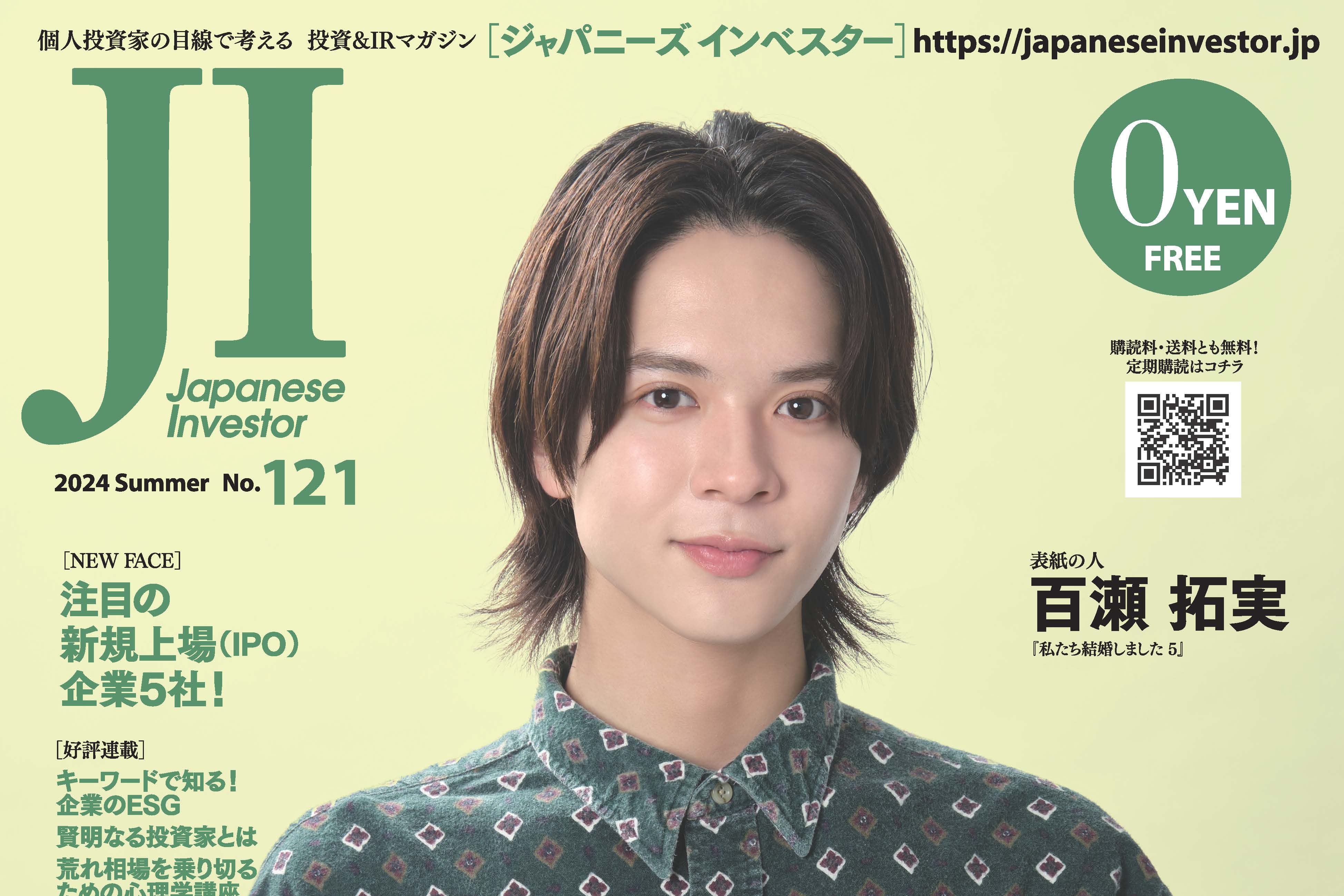雨水利用のパイオニア “ドクター・スカイウォーター”
村瀬 誠 Makoto Murase
株式会社天水研究所 代表取締役

【Profile】1949年生まれ。千葉大学大学院薬学研究科修了。墨田区の保健 所で環境衛生監視員として勤務しながら、1981年に同区で発生 した大洪水を機に雨水利用の活動をスタート。墨田区の雨水利 用に関する政策策定などに携わり、94年の雨水利用東京国際会 議では実行委員会事務局長を務めた。96年、東邦大学にて博士 号(薬学)取得。2002年、環境のノーベル賞と言われるロレッ クス賞受賞。2009年に定年退職し、天水研究所を設立。 東邦大学薬学部客員教授。NPO法人雨水市民の会理事。スカイ ウォーターバングラデシュ会長。バングラデシュ・レインウォー ターフォーラム ソサイアティアドバイザー。 http://dr-skywater.com
度重なる豪雨や洪水など、
今年も各地に甚大な被害をもたらした「雨」。
しかし、「雨水」は貴重な天然資源という側面も持つ。
今年3月には、国会で「雨水利用推進法」が成立。
雨水利用を進め、また下水道や河川に雨水が集中して
流入することを防ぐことが目的だ。
今後はさらに、雨水利用に対する
税制優遇や助成支援が広がっていくだろう。
一方、80年代初頭から雨水利用を
提唱・実践してきた村瀬氏は、今、深刻な水不足に
直面するバングラデシュでソーシャルビジネスを展開。
「雨水」のさらなる可能性を追求している。
流せば洪水、ためれば資源

御殿場の村瀬氏のご自宅は18トンの雨水タンクを備 える。18トンの水は、非常時に近隣の人の生活用水と して給水できる量。普段は、村瀬家の風呂水やトイレ の流し水などの生活用水に活用している。
「ビルを眺めていると、私にはすべて、都会のダムに見えてきちゃうんですよ」
そう言って村瀬代表は笑った。
近年、多くのビル施設に雨水を貯水する巨大タンクが設置されていることをご存じだろうか。日本で最も大きな雨水タンクを持つのは福岡ドーム。地下に約2900トン容量の雨水タンクを備える。
雨水をためるメリットは大きく4つ。まずは洪水対策。大雨の際に雨水をタンクにため、下水への流出量を抑える。次に、防災対策。初期消火や、災害などで水道が止まった時の代替水源になる。また、渇水対策としての備蓄水。そして節水対策。施設用水に雨水を利用する。雨水利用による節水効果は意外に大きく、設備費を数年で回収する施設もあるほどだ。
都庁、東京スカイツリー、六本木ヒルズ……。現在、都内だけでも1000を超えるビルが雨水タンクを導入。村瀬氏によれば、東京は世界で最も先進的な雨水利用都市だという。その先駆けとなったのが、墨田区だ。
80年代初頭の墨田区では、豪雨で下水が逆流する洪水被害が頻発。墨田区の保健所職員だった村瀬氏らは、あまりの惨状に自主的な研究グループを立ち上げ、洪水の原因が街の〝都市化〟にあることを突き止めた。
下水道は雨水の約5割が地中に浸み込む前提で設計されているが、コンクリートに覆われた地面は雨水をほとんど吸収しない。大雨が降ると雨水が下水に集中し、度重なる洪水につながっていた。
とはいえ、いまさら都市化を止めることはできない。村瀬氏らが出した解決策は「雨をためて、使う」こと。
「調査によって、墨田区の1年間の降雨量と水道使用量がほぼ同じ量であることがわかったんです。東京では水源のほとんどを上流のダムに頼っていますが、ダムの水も元をたどれば雨水。その時初めて、これまで下水に捨てていた雨水が、実は貴重な〝水資源〟であることに気づきました」
雨水利用の礎を築いた両国国技館
ちょうどその頃、台東区から墨田区へ、国技館の移転話が持ち上がった。
「国技館の予定地は、特に洪水の多い地域でした。巨大な屋根に降る雨水が一挙に下水に流れ込めば、さらにひどい洪水がおきかねない。私は保健所職員として相撲興行にあたって行政指導をしていましたので、雨水利用の導入をお願いしたのです。しかし相撲協会は法的な根拠がないこと、前例がないことから首を縦に振ってくれませんでした」
しかし、村瀬氏の考えに賛同した墨田区長が日本相撲協会を説得。ついに1984年、当時としてはアジア最大規模、1000トン容量の雨水タンクが誕生した。
国技館では、約8400㎡の大屋根に降った雨水をタンクに集め、トイレの流し水や冷房に利用。相撲興行時には、館内で使用する水の7割が雨水で賄えるようになっている。
その後、墨田区では雨水利用をルール化。東京スカイツリーの雨水利用は、このルールにより実現した。雨水利用システムは全国のスポーツドームや大規模施設に波及。ついに今年3月「雨水利用推進法」を成立させるまでのムーブメントとなった。
- 1
- 2