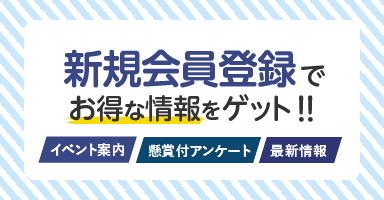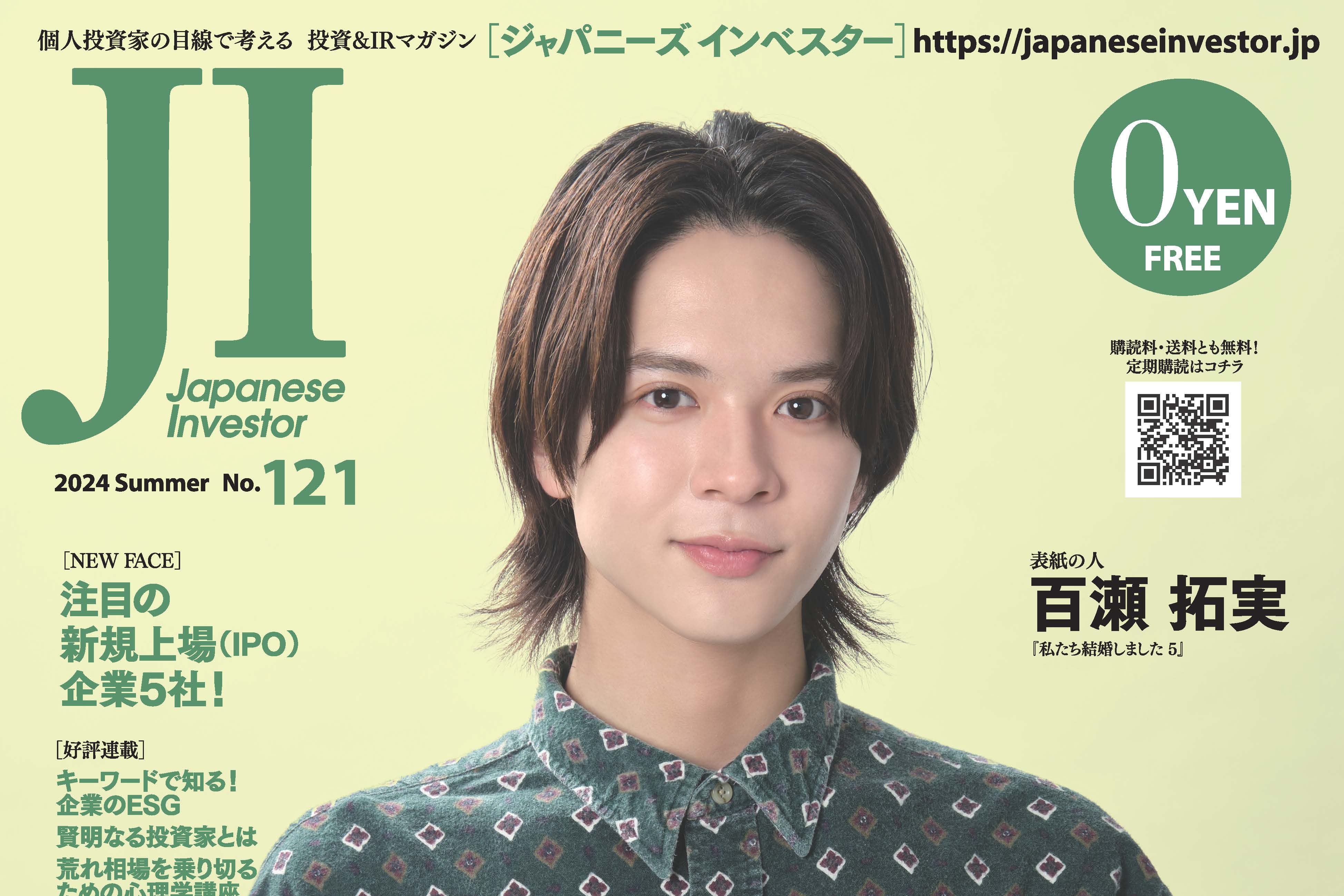儲けている時こそ「攻め」
パールハーバーで投資を考えた

のっけから私事で恐縮ですが、今年の夏は久々に長めの休暇を取ってハワイに行って来ました。到着してまっさきに向かったのが、パールハーバー。いまだに海底に沈んでいる「アリゾナ」という戦艦を前に想いをはせると、ここが70年近く前の日米開戦後であったことが胸に迫ってきます。というか、当時の日本政府の無茶苦茶っぷりには、あらためて腹立たしい想いです。だって、日本は既に中国大陸での戦争が泥沼化して、かなりネガティブな状況。それなのに、国力的に格上の米国に戦争を仕掛けて一発逆転を狙うなんて、あり得ないですよね…。
と他人を批判するのは簡単ですが、実は私たちも投資で同じような無茶苦茶をやってしまっているそうです。心当たりがないですか? 株で負けが込んでくると、一発逆転を狙って値動きが激しい株を買いたくなったり、はたまたレバレッジをかけたFXにやたらと興味がでてきたり…。スケールは違えども、まさに米国に戦争を仕掛けた日本と同じ。つまり、ネガティブな状況を打開するために、一発逆転を秘めたリスクの高い選択肢を選ぶというのは、人間に共通する心理パターンなのです。
実はこれ、「行動経済学」という分野で最近注目されています。2002年にノーベル経済学を受賞したダニエル・カーネマン教授がうち立てた「プロスペクト理論」が代表格で、簡単に理解するための質問を2つしてみましょう。
最初の質問は、下記の株のうちどちらかを買いたいかというもので、直感で答えてみてください。
a)100万円の値上がりが見込める株
b) 200万円の値上がりと、値上がりが全くない場合が半々の確率の株
では、質問その2。自分が持っている株が、下記のうちどちらだったら嬉しいでしょうか。
ア)100万円の値下がりが予測される
イ)200万円の値下がりが予測されるが、半々の確率でまったく値下がりしない
本誌読者ならお分かりの通り、どちらの選択肢も期待値、つまり確率を勘案した平均値では差はありません。a)もb)も100万円のリターンですし、ア)もイ)も100万円の損失です。だから、合理的な答は「どちらでもいい」。
でも、心理的には、世の中の多くの人はa)とイ)を選ぶそうで、ここから導き出されるのは、人間の判断は必ずしも合理的ではないと言うこと。すなわち、リターンがあるようなポジティブな状況においては確実な選択肢を選び、損失があるようなネガティブな状況においてはリスクがある選択肢を好むという心理です。
「無茶苦茶」は意外と合理的?
でも、なんでこんな不合理な心理が人間には組み込まれているのでしょうか?
その疑問を解くカギが、この連載のバックボーンになっている「進化心理学」です。進化心理学では、人類誕生の100万年前から「心のはたらき」も進化を遂げたと考えます。誕生したばかりの人類は、喜怒哀楽のようなそれこそ原始的な感情しかもたなかったのが、じょじょに微妙なニュアンスを取り込んで、複雑なメカニズムを形成していったとの仮説です。その際カギになるのが「適応」という考え方。ダーウィンの唱えた生物の進化でも出てきましたが、環境に合わせてもっとも生存の確率が高くなるように変化することですね。
では、原始時代に戻って、ネガティブな状況に直面した時を想定して、どのように心のメカニズムが適応を果たし自然淘汰をくぐり抜けたかを考えましょう。ネガティブな状況の中で最たるものと言えば、もちろん生命の危機。たとえば、狩りの途中でばったりと野生のトラに出くわしたとします。あわてて逃げ出したものの、気がつけば崖っぷちに追い詰められて、前門のトラ後門のオオカミではないですが、かなりネガティブな状況です。そんなときでも生き残れる確率が高いのは、どんな心のメカニズムを持った人?
もちろんそれは、パニックに陥って死んだフリをする人でもなければ、勇気を振り絞ってトラに立ち向かう人でもありません。むしろ、運を天に任せて後ろの崖から飛び降りるような、一発逆転を選ぶような人です。もちろん、飛び降りた人のうちの半分は頭を打ってオダブツかもしれませんが、残りの半分は生き延びて次世代に遺伝子を残すことができ、そのような淘汰がくり返されてきた結果、現代の私たちの心の中にはピンチになったら一発逆転を狙うメカニズムが凝縮されて形成されているのです。
と言う観点で見直すと、冒頭に紹介した太平洋戦争開戦の話も、別の想いが出てきます。中国戦線で負けてネガティブな状況だからこそ、乾坤一擲で米国に挑みかかるというのは、実は進化の過程で獲得した心のメカニズムにしたがった結果なのかもしれませんからね。
ポジティブな時こそ攻めよ
でも、こと投資に限っては、これは困っちゃいますよね。株で負けた分を取り返そうとアツくなってボラティリティの高い銘柄に手を出したら、かえって痛手が大きくなったなんて、本当にシャレになりません。では、どうやったらよりよい投資ができるのか? もちろん、負けが込んでいるからと言ってリスクの高い取引に手を出すのはやめましょう、となるのは当然。そして実はもう一つ大事なのは、ポジティブな時の行動です。
先ほどの質問のうち、最初の方、a)かb)かを選ぶのを読み返してみましょう。儲けがあるようなポジティブな時は、人はリスクをとりたがらないというのが、プロスペクト理論の結論です。これも進化心理学というフィルターを通して考えると極めて合理的で、原始時代のポジティブと言えば、衣食住足りているという状況。淘汰という観点では安心ですから、こんな時リスクの高いこと、たとえば余計な獲物を求めて狩りに出る必要はありません。
実際、投資でも、含み益を抱えてポジティブな状況にある時には、すっかり安心して見守るだけ。あえてリスクの高い投資先に手を出そうとは思わないでしょう。つまりは、ポジティブな領域では、心理的なリスク選好度合は、合理的なリスクをとるべき・とれる範囲を下回っているという仮説が成り立ちます。
ということで、進化心理学を投資に活かすならば、「ポジティブな時こそ攻めよ」。おりしも、株価は上昇基調。長年の含み損を解消してホッと一息、あとはボチボチやっておけばいいかな、なんて思っている方も多いかもしれませんが、こんな時こそ値動きが激しい銘柄に手を出すチャンスかもしれません。
※本稿は投資に関する基本的な考え方を解説するために作成されたものであり、実際の運用の成功を保証するものではありません。実際の投資は、ご自身の判断と責任において行ってください。
【参考文献】
菊澤研宗著
『なぜ「改革」は合理的に失敗するのか~改革の不条理』(朝日新聞出版、2011年刊)
古い体質の企業を改革しようと言う話がときどきありますが、多くの場合失敗するのだとか。その合理性に、行動経済学で切り込んでいるちょっと面白い本です。