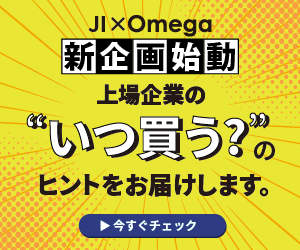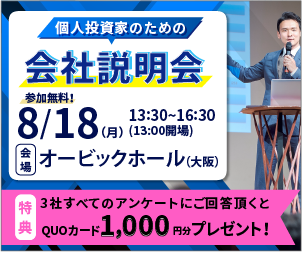11.業績と株価考察から得られる株式投資の結論
“定量成長と戦略整合性が中長期の成長期待を正当化。将来成長を一部織り込んだバリュエーション水準であっても投資妙味はなお顕在であり、投資選好は十分に維持しうる水準”
エフ・コードは、継続課金型SaaS「CODE Marketing Cloud」を中核としたデジタルマーケティング支援で確固たるポジションを築き、2023年以降はM&Aによる周辺領域(UI/UX、SEO、CRM、AIなど)への拡張と、生成AIプロダクトの投入により収益基盤を多角化している。これにより、2021年から2025年にかけての売上および営業利益はそれぞれ約15倍・14倍の成長を遂げる見通しであり、CAGRベースで見ても突出した成長トラックに乗っている点は投資判断の根幹要素となる。
足元の実績は市場期待を上回るペースで進行しており、2025年12月期第1四半期の営業利益は5.72億円、進捗率は26.0%と、下期偏重型である同社において例年を上回る高進捗である。すでに複数の買収子会社が収益貢献を始めており、今後もプロダクトのクロスセルによる顧客単価上昇が継続する限り、業績上振れの可能性は十分に残されている。
一方、株価はPER20.94倍、PBR4.34倍と高水準であり、市場は「ROE20%超を維持しながらEPSを年率+20%で成長させる企業」として同社を評価している。このような成長前提を織り込んだバリュエーションにおいては、短期的な業績未達や競合激化への感応度が高く、リスク管理の観点からは収益の季節性や新規投資のリードタイム、プロダクトの差別化持続力を注視する必要がある。
とはいえ、現在の実績EPSに対する株式益回りは約5.0%と、成長企業としては一定の収益バッファを備えている水準にあり、財務体質も健全で営業キャッシュフローの積み上がりも確認されている。自己株取得による資本政策の柔軟性も保持されており、中長期的なM&Aやインセンティブ設計においても戦略的余地を残している点は、評価を後押しする。
加えて、AI・Technology領域の急成長が今後のEPS押し上げ要因となり得ることから、従来型SaaSから“生成AI×マーケティング”への転換によるストーリー再構築が奏功すれば、さらなるバリュエーション拡張の可能性も否定できない。
現在エフ・コードは「実績のある高成長企業 × 多面的な戦略展開 × 高い資本効率性」を備えた中小型グロース株の優良銘柄である。バリュエーションには将来成長の一部が織り込まれているものの、足元の力強い業績進捗がそれを十分に裏付けており現行水準は過度に割高とはいえない。むしろ、中長期にわたる成長の持続性を評価する投資家にとっては、現時点でポジションを取ることは十分に合理的かつ戦略的な選択肢であると判断できる。短期的なボラティリティへの警戒は必要だが、「業績の質」と「経営の柔軟性」を両立させる稀有な成長株として、投資ポートフォリオにおける成長エンジンとしての役割を担える銘柄である。
12.資本利益率(ROE)の推移と現在の評価
“資本効率の改善が示す収益体質の転換。ROE20%超維持の実力と持続性を検証”
エフ・コードは、上場以降の短期間で資本利益率(ROE)を大きく改善し、2024年12月期には20.8%という高水準に到達した。これは、単に利益水準が上昇しただけでなく、自己資本とのバランスの中で効率的に収益を上げていることを示すものであり、成長株としての評価において極めて重要な定量指標である。
ROEの過去推移を見ると、2021年12月期はまだ黒字化初期段階であり、EPSは13.40円、ROE水準も10%未満とみられる。その後、2022年に一時的な減益(EPS 8.73円)を経験するが、2023年にはEPSが46.47円まで急回復し、ROEも一気に2桁後半に到達。2024年には最終的に20.8%に到達しており、成長に伴う資本効率の顕著な改善が確認されている。
このROE水準は、東証グロース市場に上場するSaaS企業の中でも上位水準であり、市場平均(おおよそ8〜12%)と比較しても際立つ。さらに注目すべきは、ROEの構成要素となる売上高利益率、総資産回転率、財務レバレッジのうち、売上高利益率の寄与が大きく、いわば“実力ベースのROE”が構築されている点である。財務レバレッジに依存せず、高収益体質に支えられた資本効率であることは、ROEの持続性を評価するうえで重要なポイントとなる。
具体的に、2024年12月期の営業利益率は27.8%、自己資本比率は33.0%前後であり、過度な借入やレバレッジに頼ることなく20%以上のROEを達成している構造である。営業キャッシュフローも堅調であり、CFマージンの高まりとともにROEとの整合性が確保されている。
市場の評価としても、ROE20%台を安定的に維持する企業に対しては、PBR 3〜5倍程度の水準が妥当とされるが、エフ・コードの現在のPBRは4.34倍。これは、ROEの継続性およびEPS成長性が市場に一定程度信頼されている証左といえる。
一方、今後の留意点としては、資本増強やM&Aに伴う株式発行等による自己資本の拡大がROEの希釈要因となり得ること、また一時的な投資増や統合コストにより利益水準がブレる可能性があることが挙げられる。ただし、現時点ではこれらの要因を吸収するだけの利益成長が確認されており、ROE低下リスクは限定的と見られる。
エフ・コードのROEは、成長ステージの企業としては異例ともいえる水準と安定性を兼ね備えており、バリュエーション評価においても中核となる定量的裏付けである。今後も20%超のROEを維持し続けられるかどうかは、プロダクトの競争力維持とグループのPMI実効性にかかっており、それらをモニタリングすることが投資判断上の重要な視点となる。
13. ROICとWACCに基づく経済価値創出の分析
“資本コストを上回るリターン創出によりROIC改善の定着が示す経済的付加価値の拡大”
エフ・コードは、収益性の改善と資本効率の向上を両立させており、ROIC(投下資本利益率)が着実に上昇している点が注目される。2024年12月期のROICは4.6%と、依然としてWACC(加重平均資本コスト)を大きく上回るとは言い難い水準ではあるものの、2021年以降のROIC改善傾向とその中身を精査すると、企業としての経済価値創出力が強化されつつあることが確認できる。
ROICは、「NOPAT(税引後営業利益) ÷ 投下資本(有利子負債+株主資本−非事業資産)」として算出されるが、同社の場合、事業資産の増加が主にM&AおよびSaaSプロダクトの開発投資によるものであり、資本コスト以上の収益を安定的に創出できるかどうかが評価の焦点となる。2023年12月期のROICは3.2%前後と見られ、2024年には4.6%まで上昇した背景には、営業利益率の向上と資産効率の改善がある。
エフ・コードの営業利益率は、2023年に12.5%、2024年には27.8%と大幅に改善しており、この利益構造の強化がROICの押し上げに大きく寄与している。また、M&Aによる連結子会社の拡大が続く中で、資本効率の悪化を回避している点は、PMI(統合プロセス)の実効性と財務管理の統制力を示していると評価できる。
一方で、WACCは、上場企業であり自己資本コストが相対的に高く評価されるSaaS銘柄として、概ね7.0〜8.0%前後と推定される。これに対して、現時点でのROICは4.6%であるため、経済的付加価値(EVA: Economic Value Added)はまだプラス圏には届いていない。ただし、2025年に営業利益が22億円、2027年には50億円の目標を掲げており、この利益成長が実現すれば、ROICは6〜8%台への到達が現実味を帯びてくる。
とくに、SaaS型ビジネスの特徴として、先行投資が回収された後は限界費用が低下し、ROICが急激に高まる「利益の収穫期」が訪れる点が重要である。エフ・コードは2023〜2024年においてこの段階に入りつつあり、今後は減価償却後のフリーキャッシュフローが急増し、ROICがWACCを安定的に上回る構造に移行することが期待される。
また、M&A戦略との整合性の観点からも、投下資本に対する利益貢献の即時性が求められるフェーズに入っており、PMIのスピードと子会社の利益率改善がROIC改善の鍵を握る。
従って、現時点でのROICはまだ資本コストを大きく超えているとは言い難いが、利益構造の強化、成長投資の成果、統合効果の顕在化という複数の要素が揃いつつあることから、今後のROIC上昇による経済的付加価値の本格的な創出が期待される。中長期視点では、WACCを明確に上回るROICの定着が、企業価値の上昇を支える決定的な要素となる。
14.フリーキャッシュフローと資本配分の視点から見る企業価値創出力
“利益成長が支える自己資金投資体制からキャッシュフローの質が問われる拡大局面”
エフ・コードは、収益成長を通じて着実にフリーキャッシュフロー(FCF)の創出力を高めており、今後の成長投資において自己資金を原資とした資本配分を実行できる体制が整いつつある。2024年12月期の営業キャッシュフローは9.1億円と、過去最高を記録。設備投資や開発投資、M&Aなどの投下資本を差し引いた後でも、黒字のフリーキャッシュフローを確保しており、キャッシュ創出能力に対する市場の信頼が高まりつつある。
特に注目すべきは、営業利益とキャッシュフローの整合性である。2023年以降、営業利益が急増する一方で、減価償却費やのれん償却がそれに追随し、キャッシュ・マージンが着実に向上している。これはSaaSモデルに典型的な「利益の収穫フェーズ」に入ったことを示唆しており、販管費や開発費の固定化が相対的に進む中で、限界利益率の高まりがCFに直結する構造へと移行している。
一方、投資活動キャッシュフローは、M&Aを中心に多額の支出を伴っており、2024年通期では10億円超の資金流出が記録されている。これはSpinFlow社、Smart Contact社などの買収に起因するものであり、資本配分としては成長性の高い分野への戦略的な投資がなされている。これらの買収は、単なるシナジー期待にとどまらず、既存のSaaSビジネスとの統合による収益性改善(PMI)を前提としている点が特徴である。
資本配分方針においては、自己株式取得(2025年春に20万株、約3.5億円)という株主還元的な政策も採用されており、資金の一部は資本効率向上に充当されている。この自己株買いは、成長投資と並行して、資本構成の最適化や将来のインセンティブ制度(ストックオプション等)にも活用される予定であり、企業価値向上と株主還元を両立する姿勢が示されている。
さらに、同社の財務体質は安定しており、ネットキャッシュポジションを維持しながら、成長投資・M&A・自己株取得の三方向にバランスよく資金を配分できている。財務レバレッジは相対的に低く、自己資本比率は2024年時点で33.0%前後。将来的に大型M&Aを実行する局面があっても、自己資本・内部留保・株式活用による柔軟なファイナンス手段を持つことは、企業のオプション価値を高める点で極めて有効である。
総合的にみて、エフ・コードのフリーキャッシュフロー創出力は、SaaS事業の収穫期到来とPMIの成果が結びついた結果であり、今後も持続的にキャッシュを創出できる限り、資本配分の柔軟性と企業価値創出能力は維持されると評価できる。投資家にとっては、利益とキャッシュの連動性、資金使途の戦略性、そして還元と成長のバランスが整った財務運営が中長期的な魅力の源泉である。