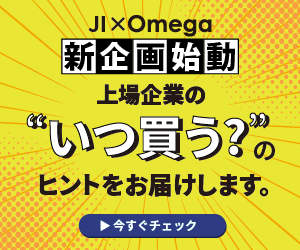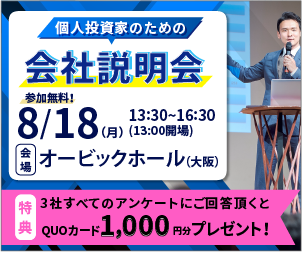3.主要株主と投資動向
“創業者主導の経営体制と長期志向の安定株主。高ROE企業としての期待を背景に株主構造が変化”
2025年7月現在の株主構造は、創業者である工藤勉代表取締役社長が筆頭株主として39.09%(約479万株)を保有しており、経営の一貫性と資本政策の自由度を保ったオーナー企業型の体制を維持している。また、他の創業メンバー・役員陣によるインサイダー持株比率も高く、全体の約64.3%をインサイダー株主が保有するなど、中長期的な企業価値創出に軸足を置いたガバナンス体制が敷かれている。
機関投資家では、国内大手のAsset Management One(保有比率5.10%)、その他法人としてマイナビ(3.29%)、Future株式会社(3.10%)が主要株主として名を連ねる。特にマイナビやFutureは戦略的提携や事業シナジーの可能性も見込まれる投資と考えられ、財務的リターンにとどまらない関係性を形成していると推察される。
なお、株式市場における流動性は堅調であり、2025年6月以降も複数のアセットマネジメント会社が新規または追加投資を行っている。たとえば、Nikko Asset Managementが2024年12月時点で1.02%(12.5万株)を保有し、2025年にかけて保有株数を増加させていることが確認されている。また、SimplexやFivestarなど小規模ながら成長株を志向するアクティブファンドによるエントリーも観察される。
一方で、2025年春には、合計2回にわたって自己株式の取得が行われた。第1回(2025年3月)は4万株、第2回(同年4〜5月)は16万株(取得価額合計3.55億円)を市場買付により取得し、総発行済株式数に対する割合は約1.6%となった。この自己株買いは、今後のM&A案件への対価対応や既存子会社経営陣のインセンティブ付与に用いる計画であり、財務の健全性を維持しながらも資本政策の柔軟性を確保する動きと評価される。
全体として、株主構造は経営安定性・成長志向の両立を図ったバランスの良い構成となっており、高ROE・高成長を志向するエクイティストーリーへの信頼が、投資行動にも反映されている。創業者主導型でありながら、戦略的外部株主との連携も強化されており、今後の資本政策や資金調達、M&A戦略においても柔軟性が期待される構造といえる。
4.中期経営計画
“営業利益CAGR50%成長を掲げる挑戦的シナリオからM&AとAIを軸としたスケーラブル戦略の展開”
エフ・コードは、2025年12月期を初年度とする3カ年の中期経営計画において、「グループシナジーとプロダクト拡充による持続的高成長」を基本方針に掲げている。数値目標としては、2027年12月期に売上高150億円超、営業利益50億円超を掲げ、営業利益のCAGR(年平均成長率)を50%以上とする極めて高い成長トラックを想定している。
本中計の根幹は、「継続課金型プロダクトの拡販 × DX領域の併売強化 × AIテクノロジーによるバリューチェーン拡張」で構成されている。具体的には、以下のような成長ドライバーが想定されている。
① プロダクトの成長加速:主力製品「CODE Marketing Cloud」を中核とするSaaS事業においては、新規顧客の獲得と存顧客の単価拡大(併売促進)が進行。加えて、チャットボット「hachidori」やEFO最適化「f-tra EFO」などの周辺SaaS製品との連携強化により、LTVの向上を図っている。
② M&Aによるケイパビリティ拡張:2023年以降、10社以上のM&Aを通じて、UI/UX改善、動画制作、エンジニア教育、コールセンター、生成AI開発など、顧客接点の上流から下流までをカバーするグループ体制を整備。今後も新規M&Aを継続的に行うとともに、取得企業の早期PMI(経営統合)による利益貢献を進める方針である。
③ AIテクノロジーの事業統合:2023年には生成AI技術を用いたプロダクト開発に着手し、2024年には「SpinFlow社」「Ciel Zero社」などのAI関連企業を買収。生成AIと既存マーケティングツールの統合によって、意思決定支援やコンテンツ最適化等の新たな価値創出が見込まれている。
中計期間初年度となる2025年12月期における収益見通しとしては、2021年12月期EPS13.40円 から 2025年12月期EPS104.84円と、4年間で7.8倍(CAGR +67%)に成長する見通しを前提としており、これは市場の織り込む成長期待(+20%前後)を大きく上回るペースでの成長実績及び見込みである。
また、組織面では、社内の技術人材・コンサルタント育成体制を強化し、AIやデータ領域を中心にDX人材の量・質の双方での拡充を進めている。これにより、拡大する顧客基盤と事業領域の対応能力を担保する構えである。
本中期経営計画初年度となる2025年12月期に関しては「売上・利益ともに2倍以上」を短期間で実現する高難易度のシナリオではあるが、すでに足元の進捗(2025年12月期第1四半期売上進捗率24.2%、営業利益進捗率26.0%)は堅調であり、初年度としての滑り出しは良好と評価できる。
5.国際事業に関して
“国内完結型モデルからの転換模索。東南アジア・北米市場への布石は限定的ながら継続”
エフ・コードの事業展開は、現時点では主に国内市場に依拠しており、2024年12月期時点での売上収益のほぼ全量を日本国内で計上している。グローバル売上比率は1%未満と見られ、短中期的にはDX需要が引き続き旺盛かつ堅調な国内の深耕・拡張に集中する方針が明確である。
過去には東南アジア(タイ・バンコク)や香港に現地法人を展開していたが、いずれもすでに清算済みとなっており、現状において海外拠点は保有していない。一方で、東南アジアや北米における企業のマーケティングDXニーズの高まり、またグローバル企業からの案件増加といった外的要因を踏まえ、今後の再進出の可能性は完全に否定されていない。
特筆すべきは、同社がM&Aによって取得した子会社の一部が、海外展開や多言語対応の機能を有している点である。たとえば、SpinFlow社はグローバルな生成AIモデルとの連携機能を開発しており、北米・欧州のクラウドインフラとの互換性を有する。また、Web制作系子会社においても、インバウンド対応や越境EC向けのサイト構築需要が増加しているとされ、こうした周辺需要をテストケースとして、段階的なグローバル展開を模索する可能性がある。
現時点での海外戦略は「機能的対応」にとどまるものの、将来的な成長余地としてのポテンシャルは十分に認識されている。加えて、国内市場における成長が鈍化する局面においては、M&Aや業務提携を通じた国外展開が中長期戦略の一部として再浮上する可能性がある。
国際事業は現段階では限定的であり、投資判断における主要ファクターではないものの、テクノロジーやSaaSという事業ドメインの可搬性の高さから、今後の成長余地としての重要な“オプション価値”を秘めていると評価できる。
6.長期の業績
“売上・利益ともに14倍超の急成長トラック。継続課金モデルとM&A戦略の複合効果”
エフ・コードは、2021年12月期から2025年12月期(予想)にかけて、売上および利益の両面で飛躍的な成長を遂げている。2021年の売上収益は6.1億円であったが、2025年の予想では100.0億円に到達し、およそ15倍の成長が見込まれている。営業利益も同様に、2021年の1.6億円から2025年には22.0億円と、14倍近い拡大を示している。加えて、EBITDAも同様のスピードで拡大しており、2021年の1.6億円から2025年の23.3億円へと推移する見通しである。また、1株当たり利益(EPS)については、2021年に13.40円であったものが、2025年には104.84円まで上昇する計画となっており、約7.8倍の成長が期待されている。
この急成長の背景には、継続型のSaaSによる安定収益基盤に加え、顧客単価の向上と併売による収益強化、さらには積極的なM&Aによる事業領域の拡張が複合的に作用している点が挙げられる。創業期はプロダクト単体での収益に依存していた同社だが、2023年以降はCRMやUI/UX改善、広告運用、エンジニア育成などの周辺領域まで事業を拡大しており、顧客のマーケティング全体を包括的に支援する体制へと進化している。特に2023年から2024年にかけての営業利益の大幅な増加は、M&Aの利益寄与と既存事業のスケール化が同時に進行した成果といえる。
EPSの推移においても、2022年にIFRS組替による遡及処理(未上場企業におけるストックオプション株式報酬の費用計上等)などの影響で一時的な減益局面(8.37円)を迎えたものの、2023年には46.47円へと大幅に回復し、2025年には105円弱に到達する見込みとなっている。この間、株式の希薄化も進んだが、利益成長がそれを大きく上回っており、1株当たり価値の向上を実現している。
また、財務基盤の面でも着実に強化が進められており、2021年時点でおよそ10億円弱だった総資産は、2024年末には約218億円に達し、自己資本比率も30%超を維持している。営業活動
によるキャッシュフローは、4年間で累計約29億円を創出しており、外部資金に依存しない内部成長力が確立されつつある。
このように、エフ・コードの長期業績は、継続課金モデルの磨き上げ、M&Aの活用、キャッシュ創出力の強化といった多面的な成長戦略が奏功した結果といえる。すでに実績として示されたこの成長軌道は、同社の今後の持続的成長可能性を裏付ける極めて重要な指標であり、投資家にとっては中長期の保有に耐えるファンダメンタルズの強さを意味している。