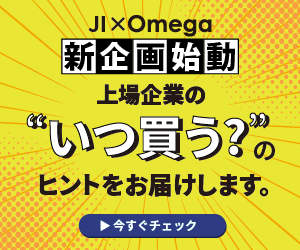7.直近の決算における業績
10.5%の増収も減益決算に。人件費上昇と報酬制度の影響で利益は一時的な調整局面へ
2024年9月期通期決算は、売上高71.65億円(前年比+10.5%)と2桁の増収を確保した一方で、営業利益は6.31億円(同▲9.6%)、経常利益6.29億円(同▲10.2%)、親会社株主に帰属する当期純利益は4.04億円(同▲7.8%)となり、減益決算となった。営業利益率は8.8%と引き続き高水準を維持しているものの、前年の10.8%からは低下しており、利益面では踊り場にある状況といえる。
収益構造上の主因として、2024年1月に実施された定期昇給に加え、売上連動型の成果報酬制度の導入によって人件費と販管費が増加。特に、エンジニア単価の上昇や受託比率の増加により売上総利益は増加したものの、インセンティブ制度が粗利改善を吸収し、営業利益率を押し下げた。これは中長期的な人材定着・報酬制度改革を見据えた構造的投資であるが、短期的には利益の伸び悩みを招いている。
一方で、「ITコンサルティング」「受託開発」「運用保守」などの戦略領域は引き続き拡大し、売上高は21.9億円、全体に占める構成比は30.5%に達した(前年は21.0億円、構成比32.2%)。SES主体だった収益構造からの高度化が進んでおり、今後の利益率改善に向けた基盤が形成されつつある。
財務面では引き続き強固なバランスシートを維持しており、営業キャッシュフローは4.81億円、フリーキャッシュフローは4.78億円と安定している。現預金残高は10.0億円、有利子負債は3.75億円(短期借入金1.22億円+長期借入金2.53億円)にとどまり、ネットキャッシュは6.3億円(第2四半期末では5億円)と、財務安全性は極めて高い水準にある。
株主還元も継続的に強化されており、年間配当は1株あたり52円(前年51円)と4期連続の増配を達成。配当性向は21.1%、配当総額は84百万円となった。さらに、自己株式の取得も48百万円実施しており、総還元性向は32.8%に達している。中期経営計画で掲げる「総還元性向30%以上」の方針に沿った運用がなされており、成長投資と資本還元のバランスを意識した資本政策が機能している。
2024年9月期の決算は戦略領域の成長と増収が継続した一方、報酬制度改定と人件費の上昇が収益に影響し、減益となった。一時的な利益調整局面にあるものの、受託案件・コンサル領域の拡大が将来的な営業利益率の回復を支える見通しであり、今後の反転タイミングと収益体質の強化が投資判断の焦点となる。
8.通期業績予想
売上高は業績予想を上方修正し89億円へ。戦略領域の拡大と単価上昇が牽引
2025年9月期通期の連結業績として、 2024年11月14日公表の2024年9月期決算短信 では売上高86.06億円、営業利益6.35億円、経常利益6.35億円、当期純利益4.04億円を見込んでいた。しかしその後、2025年5月12日に公表された「2025年9月期第2四半期決算短信」において、売上高予想を89.06億円へ、営業利益予想も6.35億円に据え置いた上で、売上面を中心に上方修正した。
この売上予想の引き上げ(+3.00億円、増加率+3.5%)は、M&Aによって連結化された子会社HCフィナンシャル・アドバイザーの新規連結効果を織り込んだものである。
営業利益の見通しは6.35億円で据え置かれているが、これは報酬制度や採用強化による人件費増加を織り込んだ水準であり、営業利益率は前期(8.8%)比で低下する見込みながらも、戦略的コスト投資とのバランスを取った着地である。営業利益率は約7.1%を想定しており、中長期の収益性回復を見越した布石として評価できる。
一方で、親会社株主に帰属する当期純利益は3.27億円(前年比▲19.0%)と減益予想に下方修正された。これは、保有する上場株式に関する評価損など、営業外要因による一過性損失が反映された結果である。なお、営業利益やキャッシュフローに関しては影響がなく、事業の稼ぐ力に毀損はない。
進捗率ベースでも、第2四半期終了時点で売上高は40.71億円、営業利益3.78億円と、通期予想に対する進捗率はそれぞれ45.7%、59.6%と、計画達成に対する信頼度は高い。下期はコンサル・受託型案件の売上計上タイミングが集中することから、業績の季節性を踏まえても上振れ余地が存在する構造となっている。
以上を踏まえると、2025年9月期は増収率+24.3%という過去最大規模のトップライン成長が期待される一方で、利益面は戦略的な人材投資を織り込んだ抑制的な計画が提示されている。営業利益は安定を維持し、評価損を除いた実質ベースでは収益力が維持されていると評価でき、株主にとっては成長戦略の進捗と同時に、財務安全性を保った慎重な利益運営体制に注目が集まる。
9.成長戦略とリスク
非連続成長に向けた戦略的布陣からM&A・戦略領域強化と人材依存リスクの管理が焦点
HCHは、2025年以降の持続的成長に向けて「戦略領域の拡大」「M&Aによるシナジー創出」「人的資本投資の最適化」という三本柱の成長戦略を軸に据えている。特に、ITコンサルティングや受託開発、運用保守といった高付加価値領域の売上構成比を継続的に高める方針を明確にしており、2025年9月期第2四半期には戦略領域売上が7.5億円、全体に占める比率36.6%にまで上昇した(前四半期比+3.5pt)。 このシフトが利益率改善と顧客ロイヤルティの向上を促進し、既存のSES型モデルに依存しない成長構造の確立につながっている。
さらに、M&A戦略においては、HCフィナンシャル・アドバイザーの完全子会社化を契機に、従来のIT開発スキームに経営・事業再編コンサルティングという視点を加え、クロスセル型のシナジー創出を生み出す顧客企業への総合ソリューション提供体制を構築。この垂直統合的モデルにより、受託案件の上流工程(業務改革、システム要件定義など)から下流工程(開発、保守運用)まで一貫して対応できる体制が強化されている。今後も、業種特化型のソリューションやAI/データ領域に特化した技術系子会社(例:TARA社)を活用し、さらなる競争優位の確立を図る構えである。
中期経営計画では、2027年9月期に売上高120億円、2030年9月期にEPS1,000円という野心的な目標を掲げており、シミュレーション*として公開されているいずれのシナリオもM&Aを含めた成長加速が前提となっている。とりわけ、シナリオCでは毎期売上+5%、利益率+0.1ptのシナジー創出が想定されており、M&A実行と統合プロセスの品質が成否を分ける重要な鍵となる。
*中長期経営方針としてコミットしたものではなく、シミュレーションとしての数値目標となっている
一方、成長加速と並行して、同社のリスク構造も変化している。最大の構造的リスクは、労働集約型ビジネスに起因する人材確保・人件費上昇リスクである。2024年9月期は、成果報酬制度の導入や定期昇給の実施により販管費が増加し、利益成長が抑制された。今後も市場全体のエンジニア争奪戦が激化する中、優秀人材の獲得と離職防止に関する取り組みの成否が利益水準に直結する。また、技術者一人当たりの生産性や稼働率がPLに大きな影響を与える構造であり、人材の定着とスキル平準化が持続的利益率確保の鍵を握る。
加えて、M&A実行に伴う統合リスク(PMI)や、成果報酬制度導入によるインセンティブ設計の複雑化など、内部管理体制の高度化も課題として残る。これらの非財務領域の強化が伴わなければ、高成長フェーズにおいて逆にコスト管理や統制の形骸化が起こる可能性も否定できない。
HCHの成長戦略は、量的拡大と質的高度化を並行して進める非連続成長モデルに立脚しており、その推進力は戦略領域の拡大・M&A実行力・人材確保力という三位一体の運営能力にかかっている。これらのバランスと内部統制をいかに高精度に運用できるかが、中期的なROE・ROICの維持、そして企業価値最大化の鍵となろう。
10.株価の動向と株式バリュエーション
バリュエーションはEPS成長を織り込む水準。高ROE銘柄の宿命と短期収益調整リスク
HCHの株価は、2024年後半から2025年春にかけて業績の上方修正やM&Aの進展、受託型案件の積み上がりなどを背景に強含みで推移した。直近株価水準(2025年7月時点)は調整後PER8.9倍*、PBR2.67倍であり、これは同業グロース市場上場のIT人材企業と比較してもやや高めの水準にある。だが、ROE33.9%という極めて高水準の資本効率を実現していること、利益の多くを成長投資に回す方針を採っていることから、バリュエーションは一定の合理性を持つと評価できる。
実際、現在のPBR2.67倍という水準は、直近3年間の平均PBR(約2.3倍)を上回っており、投資家が将来の成長シナリオ(特に戦略領域の拡大とM&AによるEPS押し上げ)をある程度織り込んでいることが伺える。EPS成長率は過去3年間で年率20%を超えており、今期予想においても売上+24.3%増、営業利益+0.7%というトップライン中心の成長が見込まれている。こうしたEPS成長期待に支えられた株価水準である点は、他のグロース企業と比べても強みとなる。
また、益回り(Earnings Yield)ベースでは9.7%と、10%近いリターンを示しており、これに加えてネットキャッシュが5億円である点を踏まえると、実質的なPERは10.7倍に調整される。財務の健全性を担保しつつ、戦略投資を継続する体制が整っていることは、バリュエーションの支えとなる要因である。
一方で、短期的にはいくつかの収益性に対する下方圧力が意識される。最大の懸念材料は、人件費の継続的な上昇と報酬制度の利益圧迫効果である。2024年9月期に導入された売上連動型の成果報酬制度は、エンジニアの離職抑制やモチベーション維持には寄与する一方で、営業利益率の圧縮要因となった。2025年9月期も報酬制度と採用強化費用を織り込んだ利益計画となっており、営業利益はわずかに前期比+0.7%とほぼ横ばいにとどまる見通しである。このように、売上高は大きく成長しているにもかかわらず、利益成長が鈍化していることは、バリュエーション再評価の際に短期的な警戒材料となり得る。
また、M&Aによる非連続成長を志向する同社にとって、今後の案件選定やPMI(統合プロセス)の精度もバリュエーションを左右する要素である。実績のない高額買収や統合不全が顕在化した場合、想定EPS成長の前提が崩れ、評価修正が一気に進行するリスクも無視できない。
加えて、同社のビジネスモデルは本質的に労働集約型であり、稼働率・稼働単価・離職率といったオペレーションKPIがバリュエーションのサポート要因になる一方、これらの変動が短期業績にダイレクトに影響する。エンジニア不足や単価下落といった外部環境変化が起こった場合、利益の弾力性は限定的となり、PER・PBRの再評価が必要となる局面が訪れる可能性もある。
*当社のPERは2025年5月12日に開示した通期業績の修正値、かつ投資有価証券評価損77百万円に係る一過性費用増の影響を除外した調整後EPSをベースに算出した値である点に留意。
HCHの現在の株価水準は高ROE・高成長・良好な財務体質に裏付けられた評価であり、中長期的なバリュエーションの持続には、戦略領域の収益性向上と人材マネジメント戦略の進化が鍵を握る。短期的な株価変動リスクとしては、人件費上昇に伴う利益成長の鈍化、および一時費用に起因する純利益の減少によるセンチメント悪化が想定されるが、調整局面では中長期のEPS成長力を信じた押し目買いの好機ともなり得る構造が維持されている。