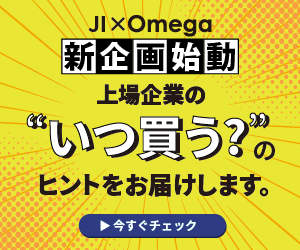3.主要株主と投資動向
創業陣と従業員による安定株主構造。事業成長に呼応した資本政策の柔軟性が鍵
HCHの株主構成は、安定株主による保有構造が維持されている。最新の公開情報(2025年7月時点)によると、代表取締役社長の富永邦昭氏が3.25%(約5.2万株)保有している。
加えて、ヒューマンクリエイション社員持株会が6.52%(約23.3万株)を保有しており、役職員を含めた社内株主比率は13%以上に及ぶ。これにより、経営陣と従業員によるインセンティブの整合性が担保されており、短期的な株価変動よりも中長期的な企業価値向上に軸足を置いた意思決定が可能な体制となっている。
外部株主のうち、最も存在感が大きいのは、営業支援や投資育成で知られる光通信(HikariTsushin, Inc.)である。同社は5.09%(約18.2万株)を保有している。光通信は、成長性とキャッシュフローの両面を重視する投資スタンスで知られ、配当利回りと資本効率の改善余地が大きいHCHの事業モデルとは親和性が高い。持分法適用には至っていないが、一定の安定株主として中長期的に保有される可能性が高い。
また、日鉄ソリューションズ(4.39%)、アドバンスト・メディア(3.11%)といった戦略的提携先による株式保有も注目される。日鉄ソリューションズはシステムインテグレーターとしてHCHの協業先でもあり、株式保有が単なる財務投資ではなく事業的な連携を視野に入れたものである可能性がある。
機関投資家による動向については、現時点でアクティビズム的な動きは確認されていないものの、総還元性向やROEの高さやPERの割安感を背景に、中小型グロース銘柄としての再評価が進む過程で、今後の保有比率の拡大も十分に想定される。
HCHの株主構成は、経営陣・社員・戦略投資家・提携先・機関投資家がバランスよく分散しており、短期的な需給リスクは限定的である。一方で、浮動株比率が高くはないため、今後の資本政策には柔軟性と透明性が求められる。中期経営計画において掲げられている「自己資本比率40%以下の維持」「機動的な自己株式取得による資本構成の最適化」といった資本戦略は、株主との対話を前提とした持続的な企業価値向上の基盤として注視されるべきである。特に、EPSの飛躍的成長を伴う場合においては、将来的な株式分割や東証プライム市場へのステップアップも視野に入る構造が整いつつある。
4.中期経営計画
“戦略領域5割化”と“EPS4〜7倍成長”の両立。段階的ステージ制で非連続成長を描く実行計画
2024年に「3段階ステージ制」による中期経営計画を策定し、売上・利益規模の拡大だけでなく、事業ポートフォリオの質的転換と資本政策の高度化を軸に、非連続的な企業価値向上を明確に打ち出している。中計の中核には、「2ndステージ(2027年9月期)」と「3rdステージ(2030年9月期)」の2つのフェーズが位置付けられており、事業構造・収益構造・株主還元戦略のすべてにおいて、定量的なマイルストーンが設定されている点が特徴である。
2ndステージでは、2027年9月期に連結売上高120億円の達成を目標としており、このうち戦略領域(ITコンサルティング・受託開発・保守運用)で50億円、SES(システムエンジニアリングサービス)領域で70億円を見込む構成となっている。これは現状比で約1.4倍の売上規模であり、特に戦略領域の売上比率を現状の約2割から4割超へと引き上げることを意味する。営業利益率の改善を伴うこのシフトは、エンジニアの稼働単価向上および案件あたり利益率の上昇に直結し、資本効率とキャッシュ創出力の両面で中長期的な改善効果をもたらすと考えられる。
3rdステージでは、2030年9月期にEPS1,000円およびROE30%以上という目標を掲げており、これを現実的なシナリオとして達成するために、「シナリオC」と「シナリオD」という2つの収益成長シナリオが示されている。シナリオCは、M&Aを通じて毎期5%の売上成長および0.1ptの利益率改善というシナジー効果を積み上げていく戦略であり、その結果としてEPSは1,016円まで上昇、親会社株主利益は6.9億円、総還元額は5.6億円に達する見通しである。これに対し、シナリオDはこれまで業績予想に織り込まれていなかった自然成長(約10%)を追加することでEPS1,850円、親会社株主利益11.7億円、総還元額7.5億円の達成を想定している。いずれのシナリオも、現在のEPS(約248円)を大幅に上回るものであり、4〜7倍の非連続的な成長を前提とした構造である点に注目すべきである。
本中計においては、事業構造の変革と同時に、資本構成の最適化を強く意識した経営方針が打ち出されている。具体的には、「自己資本比率は40%以下を維持する」ことを原則とし、資本効率の最大化を目的として、機動的な自己株式取得や配当政策を活用する方針が明示されている。また、総還元性向については30%以上を目標としており、これは今後の利益成長との組み合わせにより、自社株買いを含む積極的な株主還元余地を大きく広げることになる。
さらに、M&A戦略の位置づけが明確である点も注目に値する。2025年に実施したM&A仲介企業HCフィナンシャル・アドバイザーの子会社化は、従来のIT開発スキームに経営・事業再編コンサルティングという視点を加え、クロスセル型のシナジー創出を生み出す構造を強化するものである。今後もM&Aによる事業領域拡張は継続される見通しであり、中計の実現可否はこうした外部成長施策の実行力に大きく依存する。
このように、HCHの中期経営計画は、単なるトップラインの成長にとどまらず、営業利益率の改善、EPSの複利成長、ROE30%以上の持続、そして機動的な資本政策による株主還元の拡充を軸とした、総合的な企業価値向上を志向している点で評価に値する。定量目標の水準は高いものの、シナリオベースで成長要因と実現手段を丁寧に分解・提示している点は、株主・投資家に対するコミュニケーション戦略としても有効であり、今後の実行度合いと進捗報告に対する市場の期待も高まりつつある。
5.国際事業に関して
海外展開は極めて限定的。現状は国内完結型体制
HCHの国際事業は、現時点で全体の事業ポートフォリオにおける割合は極めて限定的であり、売上・利益への直接的な寄与は確認できない。現在の公式資料においては、海外拠点の運営や海外顧客への事業展開に関する具体的な記載は確認できず、国内市場でのサービス提供を中心とした事業構造となっている。
従って、HCHの国際事業は、直接的な海外展開やグローバル売上の獲得よりも、国内を起点とした案件の高度化における「国際補完機能の内製化」という戦略を選択している。これは、人的資本に依存するIT業界において、品質・納期・リスク管理を国内で完結するメリットを維持しながら、必要に応じて外部パートナーと連携するという、現実的かつコスト効率の高い戦略と評価できる。今後の本格的な海外進出に関しては、クライアント起点の案件誘発や、クロスボーダーM&A案件の比率増加が誘因となる可能性があるが、当面は国内事業の深化と戦略的補完の強化が国際戦略の主軸であると捉えるべきであろう。
6.長期の業績
営業利益率8.8%、ROE30%超で高い利益体質と資本効率が持続する成長実績
HCHの業績は、上場直後の2020年9月期以降、コロナ禍による一時的な需要低下を経て、堅調な拡大基調を続けている。特にエンジニア派遣を基盤としながら、受託開発、ITコンサルティングといった高付加価値領域への展開により、利益率と資本効率の双方で高水準を維持している点が際立つ。
2020年9月期から2024年9月期にかけて、売上高は45.6億円から71.6億円、営業利益は3億円から6.3億円と推移しており、売上は緩やかながら安定成長を示している。この間、営業利益率は8~10%台を維持しており、2024年9月期の営業利益率は8.8%に達している。
利益指標においても、2024年9月期のROEは33.9%、ROICは20.0%と、いずれも極めて高い水準を記録している。ROEは自己資本の効率的な活用を示す指標であり、30%超という水準は上場企業全体でも上位に位置する。特に利益の大半を成長投資に回す資本政策を採っている同社において、これほどのROEが維持されていることは、内部留保の効率的活用が実現されていることを示唆する。
キャッシュフロー面でも健全な運営が継続されている。2023年9月期および2024年9月期の営業キャッシュフローは、それぞれ7.2億円、4.8億円とプラスを維持しており、フリーキャッシュフローについても投資支出を吸収する範囲内で安定した黒字を確保している。
また、エンジニア単価および稼働率の推移は、同社の利益率を支える基礎的な指標となっている。2020年9月期から2024年9月期までの5年間で平均契約単価は55.7万円から64.5万円と年平均成長率(CAGR)3.7%で上昇しており、安定した単価引き上げのトレンドがうかがえる。稼働率もコロナ禍を経て改善し、2024年には98.4%と高水準を維持している。
このように、同社は定常的に営業利益率8%以上、ROE30%以上を実現する高収益体質を構築しており、単価・稼働率といった現場KPIの改善が着実に利益成長へとつながっている。今後も受託比率の上昇や、M&Aによる案件拡大が想定される中、これらの定量的な成果が継続可能かどうかは、投資家にとっての重要なモニタリングポイントとなるだろう。