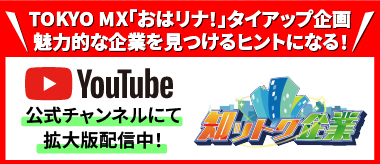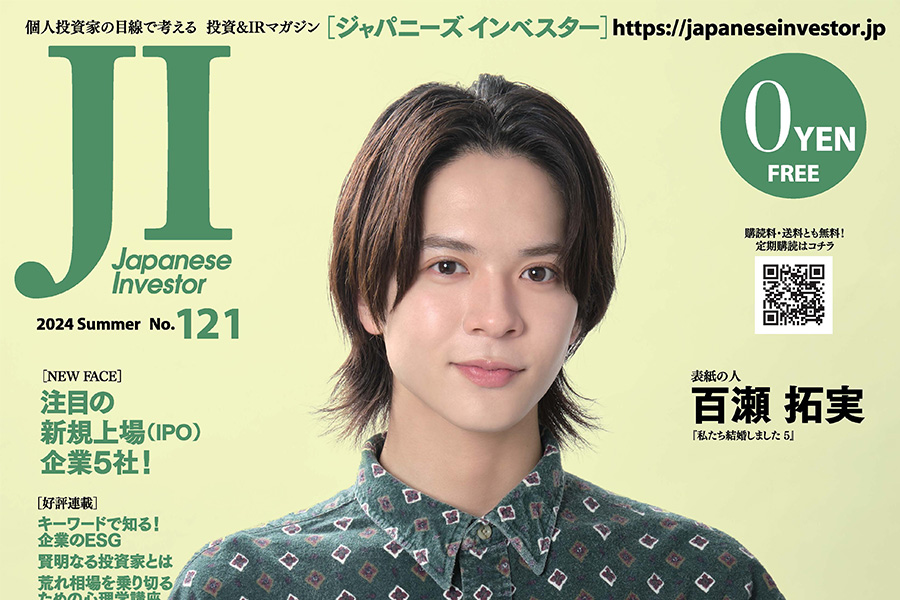「第二創業」の飛躍に向けてビジネスモデルの転換を進めていきます(株式会社日本M&Aセンターホールディングス 代表取締役社長 三宅 卓)
株式会社日本M&Aセンターホールディングス
証券コード 2127/東証プライム

代表取締役社長
三宅 卓
5か年中期経営目標「Exceed 30」を進行中の当社グループは、2023年度に社内の一体感を高めながら成約件数を拡大し、成長軌道への回帰の一歩を踏み出しました。ここでは、急速に変化するM&A市場と業界の動向を踏まえ、当社グループの目指すべき方向性と成長戦略に基づく今後の事業展開についてご説明いたします。
コンプライアンス重視経営の体制づくりに傾注
不祥事からの立ち直り状況
日本M&Aセンターグループは、M&A業務を中核とする事業展開を通じて、企業の存続と発展に貢献する専門家集団です。私たちは、自社の存在意義を表すパーパス「最高のM&Aをより身近に」を2022年に定め、翌2023年には、パーパスの実現に向けた信条と社員の行動規範・判断基準を示す「フィロソフィー」を制定し、社内への共有・浸透を図りました。
一方社内では、2021年に売上計上の不適切処理が発覚し、この不祥事及び処分をめぐり、社員の間で価値観や見解の相違が表出していました。そんな中、社員一人ひとりが「パーパス」への理解を深め、その実現に向けて「フィロソフィー」を実践していくことで、失われていた社員の気持ちの一体感を回復することができてきました。
体制としても、売上計上基準の明確化と規程化をはじめとするコンプライアンス重視の経営方針への切り替えを社内外に宣言し、CCOの採用やコンプライアンス統括部署の新設、内部相談・通報制度の周知徹底等を通じて、コンプライアンス経営の基盤は整ったと実感しています。今後はコンプライアンスを文化・風土のレベルまで浸透させることで、持続的な成長と信頼性の向上を目指してまいります。

成約件数は順調に増加し、過去最多を記録
前述の通り2022年度は、不祥事及び処分をめぐり、バラバラになった社員の気持ちをまとめながら、再発防止体制づくりに傾注した1年間でした。そして2023年度は、いよいよ業績の立て直しを図るべく、目標を見直した中期経営目標(2023年度~2027年度)の再スタートを切りました。しかし出足は思わしくなく、当初なかなか業績が伸びない状況が続きました。その理由は、主に単価の低さによるものです。単価を維持・上昇させるためには、ミッドキャップ企業(売上10億円以上または利益5,000万円以上の企業)を対象とする案件の回復が必須でした。
第2四半期からは、ミッドキャップ案件に特化した専門部署「成長戦略開発センター」の主導により進めてきた全社横断的な受託施策が奏功し、単価の上昇につながる実績を上げました。結果として2023年度の連結業績は、前年度を通じた社員の一体感の回復も寄与し、成約件数は1,146件、売上高は441億円を超えて14期連続増収を遂げ、いずれも過去最高を更新しました。利益面は、各利益段階において増益を果たしたものの、期初の目標値には届きませんでした。
成約件数が過去最多となり、単価も戻って売上高をキャッチアップしたことは、2023年度の大きな成果と評価しています。この成果は、これまで取り組んできたネットワーク営業の順調な伸長によるものです。当社はネットワーク営業を強みとしており、安定した会計事務所との提携活動を基盤に、さらなる成長を遂げています。地域金融機関とも新たな提携の形を築くことができました。具体的には、2023年7月には十六フィナンシャルグループとの合弁会社「NOBUNAGAサクセション株式会社」を設立し、事業承継・経営承継支援に関する活動を展開しています。また、今年4月には九州M&Aアドバイザーズ株式会社を設立し、肥後銀行と玉山ベンチャーキャピタルとの合弁事業を進めています。さらに、証券会社や都市銀行など大手金融機関との提携関係も拡大しています。今年6月、金融庁が金融機関に対してM&A支援を強化するよう求める監督指針の改正案を公表したことも、当社にとって追い風だと捉えています。今後もネットワーク営業をさらに強化し、新たなビジネスチャンスを創出することを目指しています。ただし、全体的にはまだ改善の余地があり、評価は60点程度と言えます。
特にダイレクトマーケティングにおいては、十分な成果を上げることができていません。この点は今後の課題として取り組む必要があります。
ダイレクトマーケティングは、金融機関や証券会社、会計事務所などから受託案件の紹介を受けるネットワーク営業と異なり、紹介料が発生しないため、高い粗利益率をもたらします。当社グループの受託案件は従前、ネットワーク経由が6割、ダイレクトマーケティングが4割という比率でした。しかしダイレクトマーケティングの方は、会計不祥事でダイレクト部門で積極的な営業施策を実施できない時期が続いたため、この比率が崩れて利益率の悪化が生じています。また経費構造も、このところコロナ禍の影響や不祥事対応などによって膨らんできており、収益性の観点から見直しが必要になっています。ダイレクトマーケティングの強化と経費構造の見直しを図り、しっかり利益率の改善につなげてこそ、100点満点の評価が可能となります。
ダイレクトマーケティングの強化は、事業戦略面でも重要なテーマとして捉えています。一昔前とは異なり、近年はM&Aの意義や有効性が一般的に広く認知されるようになりました。M&Aは事業承継や成長戦略の手法として経営者により一層重要視されており、私たちはM&Aのニーズや悩みを抱える経営者に直接コンタクトすることが重要になってきました。すなわち「M&AのBtoC化」とも言える状況となる中で、競合する新興のM&A仲介専門業者などの営業活動はダイレクトマーケティングに特化しているため、シェア確保のためにもダイレクトマーケティングを強化する必要があります。
市場環境の変化に対応し、パーパスを実現
このように、M&A業界には近年様々な変化が生じ、当社グループの主戦場である中小企業のM&A市場にも新たなニーズや課題が広がっています。その中で私たちは、自らが果たすべき社会的責務を再認識し、「パーパス」実現への想いを強めています。まず、マーケット及び業界を展望し、当社グループに求められる変化への対応について述べます。
中小企業を中心とする事業承継型M&Aの潜在需要について、株式会社矢野経済研究所の算定によれば、2035年をピークに、2025年から2045年までの20年間は、潜在需要は9万社台(売上1億円以上)を維持すると予測されています。そうした傾向を示す状況として、足もとでは経営者の高齢化による中小企業の廃業が大きく増加しています。具体的には、2025年には約245万社の中小企業経営者が70歳を超え、その中で後継者不在の会社が約127万社、うち約60万社が黒字企業と言われています。黒字の60万社が廃業を余儀なくされるということは、高度な技術や価値あるものづくり・サービスがなくなる、あるいは地域文化の担い手を失うなど、我が国にとって大きな損失を招く事態と言えるでしょう。これを防ぐため、M&Aの当事者企業に対する事業承継・引継ぎ補助金の交付や、買い手企業への税制優遇などが行われており、マーケットに追い風が吹いています。
日本が抱えるもう一つの問題は、ご承知の通り少子高齢化に伴う就業人口の減少です。生産年齢人口と呼ばれる15歳から64歳までの人々の数は、2010年時点の約8,000万人から、2035年には約6,500万人へ、2050年には約5,000万人へ減少すると予想されています。企業は労働力不足への対応が求められていますが、省人化への設備投資や社員教育による生産性向上、DXによる業務革新といった施策は、いずれも規模の小さな事業者にとって実施が困難です。そのため政府は、生産性向上のために企業を集約し、業界再編を促進する方針を打ち出しています。これにより、2030年頃には「業界再編型M&A」が激増し、従来の事業承継型M&Aとともにマーケットを拡大していくと予想されています。
現在の日本では、事業を拡大したい中堅企業にとって非常に厳しい状況が続いており、オーガニックな事業活動だけで持続的な成長を遂げ、企業として存続することは、ますます困難になってきています。当社グループは、「オーガニック成長からM&Aを活用したレバレッジ成長へのシフト」という時代のニーズに応える観点からも、業界再編型M&Aへの対応にも一層注力していきます。
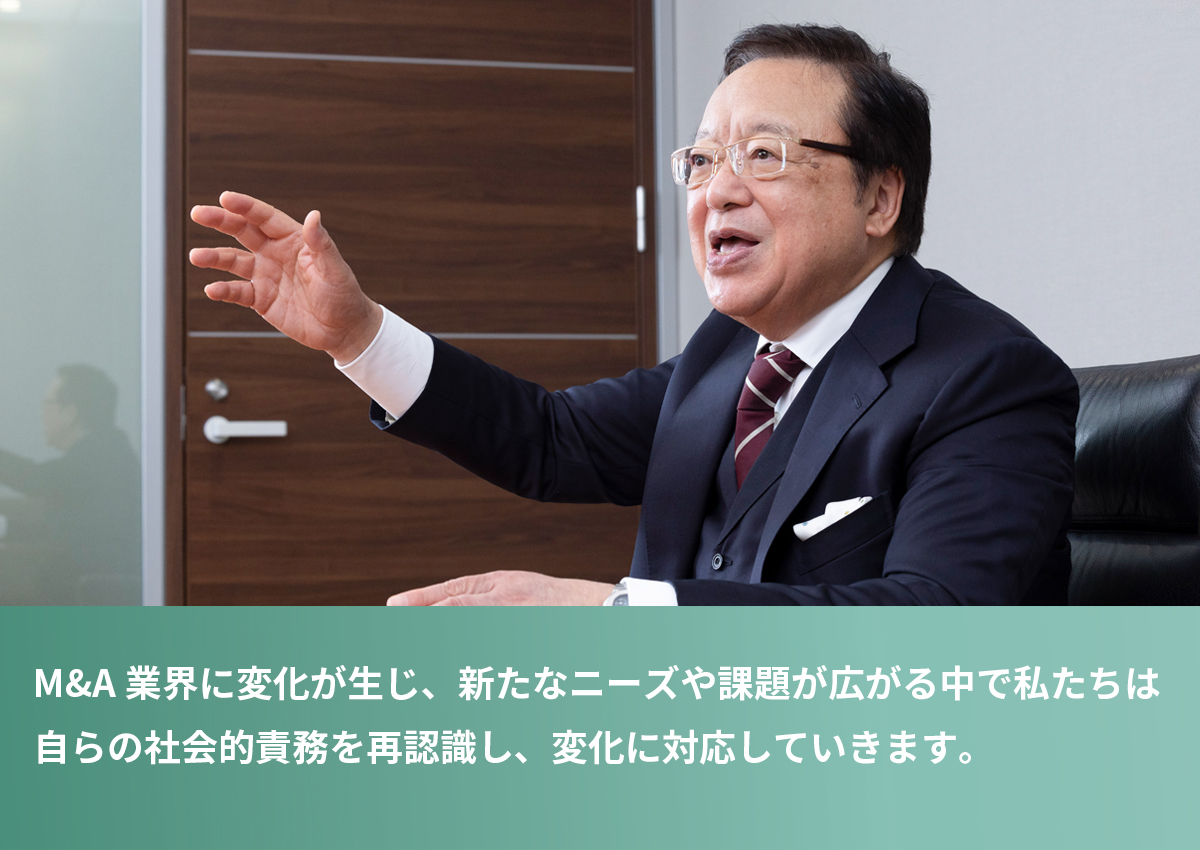
再成長に向けて一歩踏み出していく年へ
人材育成と営業施策の拡充
市場の変化を注視しながら、2024年度は再成長に向けて一歩踏み出す年と位置づけています。営業活動には一層の勢いを持たせるため、当社グループはさらなる強化策を展開しています。まず、人材採用の強化と離職率の低減・定着率の改善です。
人材採用は、質・量をともに充実させることがテーマです。私自身を含め経営陣も会社説明会などに参加し、即断即決面接を実施するほか、リファラル採用を展開するなど積極的な採用活動を進めています。2024年度は、コンサルタント職120名の純増を計画しています。
離職率の低減と定着率の改善については、中堅社員の定着が重要なテーマとなっています。日本の転職市場では40歳を過ぎての転職は困難と考える人も少なくありません。当社社員の平均年齢は34歳であり、当社に入社して経験を積み、中堅社員となった30代後半は、自身の未来やキャリアを見つめ直すタイミングであり、退職を選ぶケースも存在します。この課題に対処するため、私は中堅社員とのキャリアについての対話を行う「麻布プロジェクト」を立ち上げました。「麻布プロジェクト」では、私自身と中堅社員が麻布のレストランで食事をしながら互いのキャリアについて深く話し合う機会を設けています。このプロジェクトを通じて、中堅社員の離職を防止することを目指しています。また、かつてストックオプション制度を利用していた中堅社員も存在しますが、現在は新たなストックオプション制度はありません。この変化が退職に少なからず影響を与えていることも認識しています。そこで、私たちは100%応援型社員持株会制度を導入しました。さらに、四半期ごとの社員向けの決算説明会を新たに実施することで、社員のエンゲージメント向上を図っています。これらの取り組みにより、中堅社員の定着率を改善し、離職を防止することを目指しています。
そして採用した多くの人材をきめ細かくマネジメントできる体制を構築するため、さらに、中期経営目標を確実に達成できる体制を構築するために2024年度は5事業本部を解体し、11のチャネル制度を敷きました。11名のチャネルリーダーのもと、36名の部長職と60名のグループリーダーを配し、指導・管理する部下の人数や案件数の適正化により、細やかな人材育成を行っていきます。
またチャネル制の導入は、人材施策としてだけでなく、策定した営業戦略の遂行においても、所轄の明確化によって効率とスピードを上げ、オーナーシップを持った展開を図れるものと期待しています。
一人ひとりの社員が自身のキャリアを真剣に考え、成長できる環境を整えることで、組織全体のパフォーマンス向上を目指します。
2024年度は、コンサルタント職の積極採用への人材投資に加え、ダイレクトマーケティングの強化に向けた戦略投資、生産性向上のためのDX投資、海外事業やフィナンシャル事業領域の拡大への事業投資などを本格化します。そのため連結業績は、増収・増益を見込みながらも、経常利益率の一時的な低下を想定しています。これについては、後ほど説明させていただきます。
中期経営目標の初年度進捗と今後の展開
ガイドラインを超えるトップライン拡大を達成
現在進行中の中期経営目標「Exceed 30」(2023年度~2027年度)は、不祥事の影響による成長戦略の遅れを踏まえ、従前の目標を見直して再設定したもので、最終年度の連結業績における「売上高762億円」「経常利益305億円」の達成を目指しています。
既出の通り目標初年度は、M&A成約件数を着実に伸ばし、ガイドライン(単年度目標)を超えるトップライン拡大を果たしました。引き続き2024年度もトップライン先行型の成長で目標を引っ張っていく考えです。今は、私は収益を追いながらもトップラインを伸ばすことが最も大事だと認識しています。トップラインを伸ばすことなく経常利益を確保しても、それは経費の削減にすぎません。人材投資や営業投資の抑制で増益を果たすことはできますが、それでは2年後、3年後に業績を拡大できなくなってしまうでしょう。その意味で目標初年度の売上高がガイドラインを超えたことは、私にとって大きなブレイクスルーなのです。
この増収に自信を得て2024年度は、先に述べました人材採用をはじめとする成長への先行投資を積極的に進めていきます。そのため2024年度は、経常利益率の一時的な低下を想定し、経常利益のガイドラインを170億円と保守的に設定しました。もちろん思惑としては、ガイドラインを超える利益の上乗せを狙っており、売上高の伸びによって、十分に可能だと考えています。
中期経営目標の達成に向けた生産性向上
「Exceed 30」最終年度(2027年度)の目標達成に向けた条件として、特に求められるのは、一人当たり生産性の向上です。量の拡大と同時に単価を引き上げることは、決して容易ではなく、単価を維持するだけでも努力が必要です。
私たちは、一人当たりM&A成約件数を高めつつ、単価を維持することで生産性向上を図っていく方針です。具体的には、3,800万円から4,000万円の単価をキープしながら、一人当たり3件を超える成約件数を目指します。
そのために案件処理のリードタイムの短縮と、成約率の向上を目指します。これは顧客満足にも寄与します。
「第二創業」に込めた想い、そして目指すもの
リーディングカンパニーとして果たすべき責務
良好な市場環境を背景に、M&A業界では近年、M&A仲介専門業者が急速に増加しています。国内では現在、600社を超えるM&A仲介専門業者が活動し、そのうち85%ほどが設立2年以内、社員数4名以下の新興・小規模の事業者と見られます。乱立と言える状況の中でモラルや業務品質の低下が起きており、業界全体の健全化が大きな課題になってきました。中小企業庁からは、業界健全化の指針を示す「中小M&Aガイドライン」が公表され、また業界内からも、私が初代の代表理事を務める形で2021年に一般社団法人M&A仲介協会を発足し、適正・公正かつ円滑なM&A取引を促進すべく、自主規制などによる働きかけを行っています。
今一度、当社グループのパーパス「最高のM&Aをより身近に」へ立ち返ると、私たちが目指しているのは、すべての企業が安心してM&Aに取り組める社会であり、その実現に向けて、業界全体の業務品質と顧客満足、コンプライアンスを高めることは、リーディングカンパニーである当社グループの責務と考えます。
業界再編型M&Aの増加という市場の変化、そして新興のM&A仲介専門業者の増加という業界の変化の中で、私たちが意識するのは、明確な差別化です。当社グループがM&Aに臨むスタンスは、他社と大きく異なります。私たちにとってM&Aは、単なるビジネスではありません。創業者や従業員のみならず、事業に携わるすべての方々とご家族も含め「会社は人生を紡ぐ場所」であると考え、そのサクセッションプランを引き受けるのが、当社グループの役割です。そこには覚悟が求められますし、譲渡企業側にも譲受け企業側にも覚悟を持っていただきたいと思っています。そのために着手金を受け取り、丁寧に仕事し、最高の業務品質を提供する。そして世界最高の成約率を達成し、顧客満足も世界最高を目指していくのが、M&Aに臨む当社グループのスタンスです。私はパーパスを通じて、このスタンスを社員に伝え続けています。
サクセッションプランの場となる二つの会議体
2021年に創業30周年を迎えた当社グループは、「第二創業」をキーワードに掲げ、「全員が創業者」という想いをもって新たな一歩を踏み出しました。
この「第二創業」という言葉に託したのは、創業以来の成長の歩みから、さらに上へのステップアップを目指すという意味だけではありません。
第二創業には二つの意味が込められています。
第一の意味合いは「時代へ向けた変革」です。
これからの私たちは、冒頭に申し上げました事業承継型M&Aの潜在需要と業界再編型M&Aの拡大による市場の変化、それに伴う企業経営者の意識の変化、そしてM&A仲介専門業者の増加によるM&A業界の変化を踏まえ、これらに対応したビジネスモデルの転換が必要であると認識しています。その中で、当社グループに在籍するすべての社員が「第二創業」の創業者となり、皆で持続的成長を実現したいと考えています。
そして二つ目は経営のサクセッションです。
当社グループの将来を見据え、私自身が念頭に置くべきテーマは、自分の後継者人材を育成・選任していくサクセッションプランの実行です。今年72歳となった私は、今のところ心身の健康を維持していますが、いずれ訪れる気力・体力の低下により現在の役職を退くことを見据えて取り組まなくてはなりません。その取り組みは、3年ほど前からスタートさせ、新しい時代に合った企業グループづくりとともに着実に進めています。これが「第二創業」という言葉に託したもう一つの意味です。
2023年、ホールディングス体制の経営組織として、経営会議の下にM&A領域の事業会社を統括する「M&Aストラテジック会議」と、ファンド領域の事業会社を統括する「フィナンシャルストラテジック会議」を設置し、運営を開始しました。二つの会議体は、それぞれの領域で戦略面の連携を図り、シナジーを発揮していきます。また、両会議体は当社グループ全体の中でそうした中間持株会社的な役割を担うだけでなく、グループ経営の後継者を輩出するサクセッションプランを担う場としても機能します。
フィナンシャルストラテジック会議の方では、2023年に株式会社日本投資ファンドの社長を大槻昌彦に任せ、M&Aストラテジック会議の方は、2024年に株式会社日本M&Aセンターの社長を私から竹内直樹へ引き継ぎました。両会議体における意思決定の質は、私が中心となって進めていた時よりも、はるかに高くなっていると感じますし、いつでもサクセッションできる状況に近づいていると言えるでしょう。
マテリアリティとESGによる共通認識の形成
当社グループは、自社及びステークホルダーにとっての重要度を考慮し、事業を通じた社会課題の解決のために重点的に取り組むべきテーマをマテリアリティ(重要課題)として定めています。このマテリアリティは、「M&A総合企業としてのさらなる発展」「イノベーション」「安全安心なM&A」「社会への貢献」「人的資本経営の推進」「情報管理の強化」「ガバナンス基盤の強化」の7項目から構成されています。マテリアリティは、外部環境の変化と社内の取り組み状況を鑑み、必要に応じて見直しを行うことで、持続的な成果を追求しています。
マテリアリティの再評価では、経営会議メンバーがそれぞれの立場から意見を述べ、共通認識を形成しています。このプロセスには大きな意味があると感じます。さらにマテリアリティを社外に発表することで、株主・投資家の皆さまをはじめとするステークホルダーとの間にも共通認識が形成され、良好な関係づくりに寄与するといった効果を期待しています。
同じことがESG/サステナビリティテーマへの取り組みについても言えます。海外IRロードショーなどで欧米の機関投資家と対話する場では、特にESG経営への取り組みが重視され、大きな評価基準となっています。この観点からも、ESG/サステナビリティは重要なテーマであると認識しています。例えば、ダイバーシティ&インクルージョンにも積極的に取り組んでおり、年に1度社員向けにダイバーシティ&インクルージョンイベントを開催しています。さらに、ESGを加味した企業評価に向けた研究も進めています。
私たちは、事業活動を通じて、環境保全への貢献と社会価値の提供、強固なガバナンスの保持に注力し、多くの人々に支持していただける共通認識の形成に努めてまいります。ESG/サステナビリティへの取り組みは、私たちの企業価値の向上に欠かせない要素であり、持続可能な未来を築くための重要な取り組みと位置づけています。
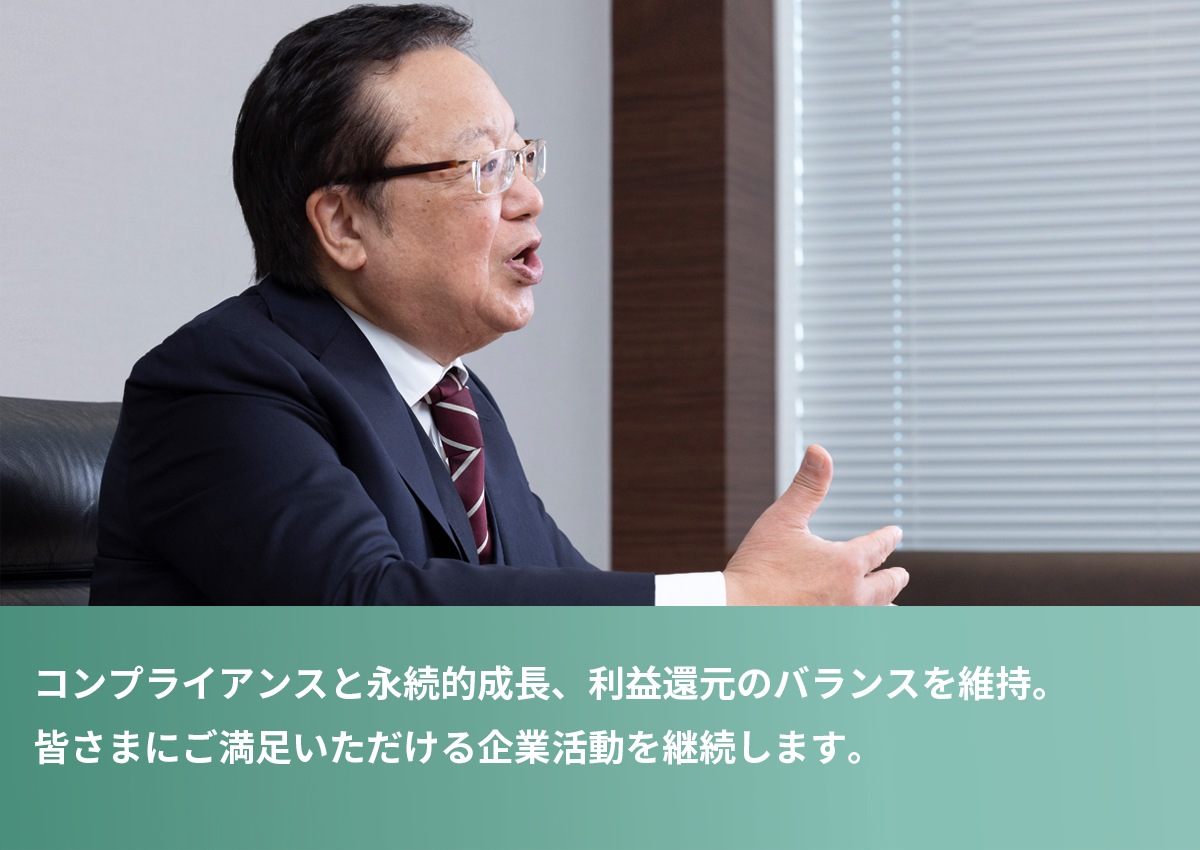
ステークホルダーの皆さまと分かち合う未来
当社は、利益還元の水準を高めるために業績の向上に全力を注ぎ、資本効率の改善を通じて株主・投資家の皆さまのご支援に報いてまいります。
おかげさまで当社グループは、再成長のスタートラインに立ち、成約件数及び売上高の順調な拡大に自信を深めることができました。今後も利益面において「Exceed 30」の期間中にキャッチアップを果たし、成長投資を次なる飛躍へとつなげてまいります。
そして昨年度同様にコンプライアンスと永続的成長、利益還元の3つを高度なバランスで維持し、ステークホルダーの皆さまに満足していただける企業活動を継続してまいります。今年度からは、譲渡制限付き株式報酬制度を導入しました。これは、先にご紹介した100%応援型の社員持株会制度と併せて制度を運用され、役員も社員も株主の皆さまと一体となった経営を実現する一助となるでしょう。
ステークホルダーの皆さまには、当社グループが実現していく未来にご期待いただき、これからも長期にわたるご支援を賜りますようお願い申し上げます。私たちは、ステークホルダーとの緊密な連携を通じて、持続的な成長と価値創造を追求し続けます。引き続き企業活動を展開し、皆さまとともに未来を築いてまいります。
※本記事は、株式会社日本M&Aセンターホールディングス「統合報告書2024」より転載しております。