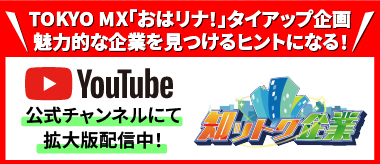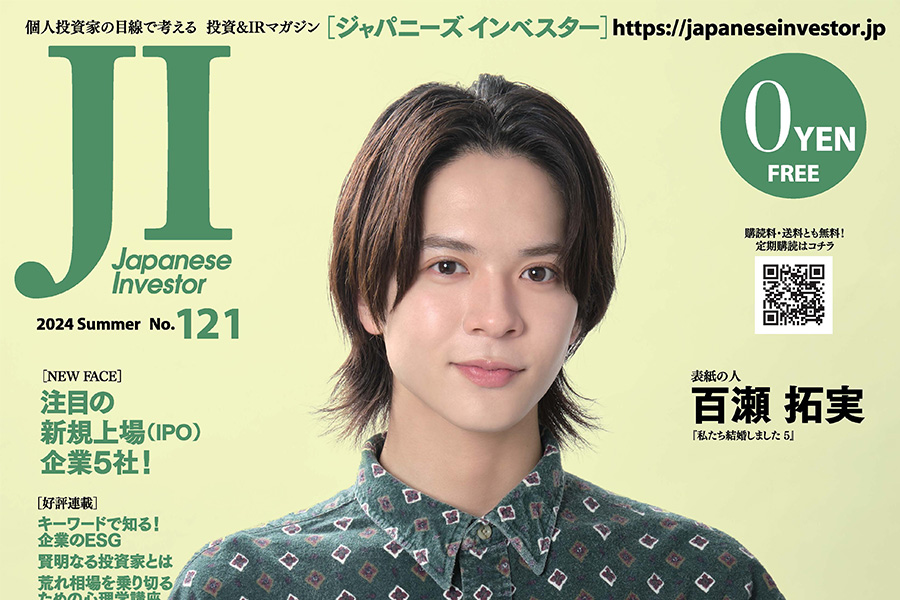第24回 『私の財産告白』 本多静六著から学ぶ

さわかみ投信株式会社
常勤監査役
本多 正之
ほんだ・まさのり。1966年横浜市立大学商学部卒。同年野村証券に入社。ロンドンや東南アジア、更に米国西海岸のカルパース等の機関投資家訪問を通じて、何度も日本株ブームを巻き起こした理論派営業マン。その後、ベンチャーキャピタルやヘッジファンド運用会社の経営に携わり、2006年さわかみ合同会社入社。2009年より現職。
小生は、約半世紀にわたって広義のインベストメントの世界に係わらせていただいてきました。その経験から学んだことは、「多少のタイムラグはあるにせよ経済と株式市場はほぼ連動し、超長期で約六〇年、長期で約十年、中期で約五年前後の景気・相場環境のうねりをなしてきたな」という実感です。特に暴落の跡をチャートで追跡するにつけいろんな共通項を見出すことができ、つくづく「危機は機会の入り口だ」と痛感させられます。
一方で「株に投資するということは、企業の価値創造に参加させていただくことなのだ」という基本の確認です。「株価は企業の実態を映す鏡」とはよくいわれます。ただ株価はその時の国内外の政治的、経済的状況等の要因により、買われ過ぎたり、売られ過ぎたりします。しかしながら時間の経過とともに株価が実態価値に近づいていく習性は間違いなくあると思います。長期投資運用が比較的有利だというのは、このような経済・株式市場の大小のうねりを見極めながら、売買のタイミングをとりやすくなるからだと信じます。
ところでいままで国内外の賢明な投資家についていろんな本を読んできましたが、小生が最も感銘を受けたのは本多静六博士です。ただ賢明な投資家というより、彼の人生哲学に魅かれたというのが本音かもしれません。
Ⅰ.本多静六博士という人物
本多静六博士(旧姓・折原/一八六六年~一九五二年)は現在の埼玉県久喜市に生まれました。明治、大正、昭和にわたり、文字通り激動の時代を東京農科大学(現・東大農学部)で学究生活と執筆生活、その間およびその後も、日比谷公園・明治神宮神苑等、日本中の百以上の公園の造園・森の植林等を行ってきました。一方で独自の蓄財投資法と生活哲学を実践して莫大な財産を築いた投資家としても有名です。また、生涯で三七〇冊余の著作を残され、特に八五才で上梓した『私の財産告白』(二〇〇五年新装版・実業之日本社)の序文では、「偽善ないし偽悪の面をかなぐり捨てて真実を語った」と吐露しております。そして翌々年には肩の荷をおろしたかのように亡くなりました。
Ⅱ.掲題の本から何を学ぶか
彼が生きた八十六年間ほど日本が激変した時代はなかった、といっても過言ではないでしょう。今後どのような事が日本に起きようとも、彼の生きた時代以上の激変はまずないでしょう。そこで、これからの未知の時代を生きていく上でも、心の支えとなるであろう箇所を二点だけ同書から抜粋させていただきましょう。
①人生計画
二十五歳で次のような人生計画をたてた。「四〇才までは勤倹貯蓄、生活安定の基礎を築き、六〇までは専心究学、七〇まではお礼奉公、七〇からは山紫水明の温泉郷で晴耕雨読の楽居。」……結果的にほとんどこの計画に沿った人生をおくってきたが、常に本業専一にして仕事を道楽化させてきた。つまり己の仕事に全身全力を打ち込んでかかれば、日々の勤めがおもしろくてたまらぬという意味での道楽だ。モットーは「人生即努力、努力即幸福」。
②天引き貯蓄と運用
二十五歳から四〇歳まで、収入の四分の一を強制的に天引き貯蓄し、臨時収入とバイト代はまるまる貯蓄した。とにかくお金というのは雪だるまのようなもので、初めはほんの小さな玉でも、その中心になる芯ができると、あとは面白いように大きくなってくる。貯蓄がある程度進んだところで株式投資にすすんだ。投資の第一は安全確実である。しかしながら、絶対安全をのみ期していてはいかなる投資も手も足もでない。だから絶対安全から比較的安全、というところまで歩みよらねばならぬ。また大切な処世信条として、何事も『時を待つ』ということだ。あせらず怠らず、時の来るのを待つことが肝要である。
渋沢栄一翁、安田善次郎翁あるいは後藤新平等、明治を代表するような大人物との親交のあった彼は、今の言葉でいえば内部者的な取引もあったことでしょう。しかしながら一九二七年(昭和金融恐慌の年)、六〇才で東京帝国大学停年時には、「人並み外れた大財産や名誉の位置は幸福そのものではない。身のため子孫のため有害無益である」と悟り、匿名で財産のほとんどすべてを社会事業に寄付してしまいました。決して守銭奴ではなく、それどころか賢明なる偉大な大投資家であったわけです。
Ⅲ.景気・株式相場のうねりの捉え方

MCGの推移(2000年1月~2014年8月)
静六翁は投資に関しても『時を待つ』ことの重要性を強調されました。ただ彼の著書に、経済と株式との関わりで、そのことを具体的に書いたものを見たことがありません。そこで現代の市場の過熱感または人気離散度を自分なりに「見える化」した指標をご紹介しましょう。ただこの指標は将来を予測するものではなく、あくまでも現在の位置を教えてくれるものだと理解すべきでしょう。
東証株価時価総額(Market Capitalization)÷日本の名目GDP=MCG(%表示)がそれです。なお東証株価時価総額は東証発表の東証一部、二部、ジャスダック、マザーズ等すべての時価総額を含み、名目GDPは内閣府発表の前年度の数字を使っています。
二〇〇〇年一月~二〇一四年八月までの毎月末MCG指標が、八〇%以上だった期間は約三分の一、一方六〇%未満だった期間は約四分の一となります。
ところで、数多くある相場の諺の中で小生が最も好きなものは、Bull markets are born onpessimism, grow on skepticism,mature on optimism and die oneuphoria.(上昇相場は悲観の中で生まれ、疑いの中で育ち、楽観の中で成熟し、熱狂とともに終わる。/ジョン・テンプルトン氏)です。自分のなかでは、この指標が六〇%未満が悲観帯(買い時)、八〇%以上は成熟、そして百%以上が熱狂の要注意帯と考えてまいりました。
もっとも、長期投資のドルコスト平均法を活かした積み立て投資や、確定拠出年金(DC)のような超長期の投資は、このようなうねりはそれほど気にする必要はないでしょう。ただ勉強のために少しメリハリをつけるのも一考かもしれません。
なお、以上は、小生が常勤監査役として勤めるさわかみ投信(株)の運用方針とは全く関係なく、あくまでも古老の個人的見解にすぎません。
※本稿の内容は筆者の個人的見解に基づくものであり、所属する組織の意見等ではありません。