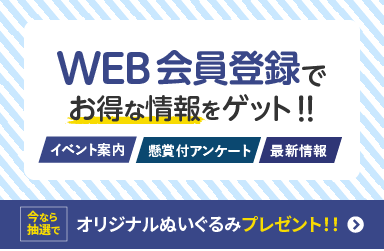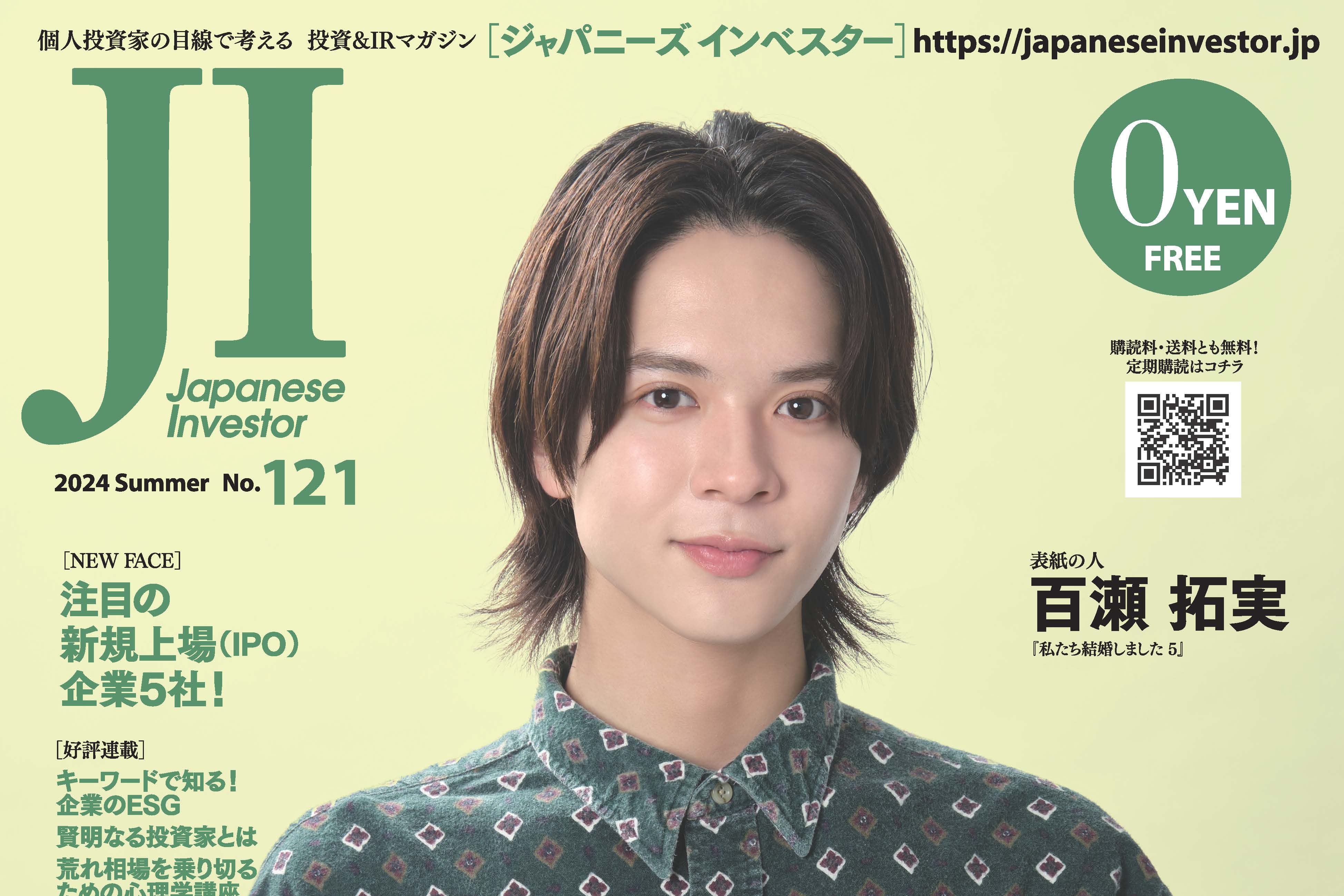社会が抱える教育問題をeラーニング教材で解決――株式会社すららネット 代表取締役社長 湯野川 孝彦
株式会社すららネット
証券コード 3998/東証マザーズ
代表取締役社長 湯野川 孝彦
Takahiko Yunokawa

一流校を目指す学習塾は数多くあるが、不登校や経済的困難といった問題を抱えた子どもに向けた学習塾は少ない。すららネットはeラーニングによって親子が直面する問題の解決を図る。本業が社会貢献に直結する事業を率いる湯野川孝彦社長に教育現場の現状と事業の将来性を聞いた。
取材・文/山本 信幸 写真撮影/和田 佳久
個別指導塾の弱点である教える品質のばらつきを解消
── eラーニング教材であるクラウド型学習システム「すらら」は、湯野川社長が前職で企画・開発したそうですね。
湯野川 FC(フランチャイズ)本部を支援する会社にて2004年から個別指導塾チェーンの支援に携わったことが教育との最初の接点です。経験の無い分野だったので、スーパーバイジング(店舗の指導やチェック)代行や加盟開発販売代行を適切に行うためには、自分たちで塾を経営してみる必要があると考え、個別指導塾を運営したところ、いろいろな問題点に気がつきました。
個別指導塾に来る生徒さんは学力が低い子が多いのですが、教え方を工夫しても成績がなかなか上がらない。原因は個別指導塾の構造的な問題にありました。学生アルバイトが教えるので、教える能力や教え方にばらつきがあり、教務品質が安定しないのです。また学習が遅れている生徒さんは毎日通う必要があるのですが、その分月謝が高額になります。
eラーニング教材を使って学ぶ仕組みを作れば、そうした問題を解決できると社内提案をして認められました。eラーニングならば塾長一人で運営でき、毎日通っても月謝を抑えることができます。
「すらら」にはアダプティブラーニング機能と呼ばれる生徒の学力に合わせて問題の難易度を変える機能があり、簡単すぎて飽きてしまうことも、難しくて嫌になってしまうこともありません。このような仕組みにより順調にお客さまは増えていたのですが、当時は赤字事業だったため続けられなくなり、2010年にMBOにより事業を買い取りました。
主要販売先は学習塾だがAIの活用で家庭向けも強化
── 主力の販売先は学習塾や学校というBtoBのビジネスなのですね。
湯野川 学力が低い生徒さんは自宅で学習する習慣がないことが多く、教材を提供しただけではログインしてもらえません。そこでメインの販売ルートは生徒さんをサポートする人がいる学習塾や学校としています。ここ1、2年で契約が増えているのは地方の大手・中堅学習塾ですね。地方では少子化の影響で生徒を集めにくくなっており、人件費をかけずに塾を運営する必要に迫られています。
── それは業績にどう反映されているのでしょう。
湯野川 当社の主な売上は「導入校数×サービス利用料」「ID数×ID利用料」になります。導入校は2010年の144校から増え続け2017年は693校(9月末現在、海外校を含む)になりました。ID数は2016年12月末から1万ID以上増加し、2017年12月期は過去最高売上、最高益となりました。
収益を上げやすい一流校を目指す教育市場には大手が参入していますが、当社はeラーニングの強みを生かして、とことんその逆を行ったところ、子どもの学習に悩む親御さんから大きな支持を得ることができました。教科書と参考書だけでは勉強ができない子ども、人(教師)と接するのが苦手な子どもも「すらら」のアニメのキャラクターなら受け入れてくれるし、インタラクティブで褒められることでモチベーションも高まります。

──BtoCの事業について教えてください。「人」は介在しないのですか。
湯野川 「すららコーチ」という地域の学習塾の講師がサポートし、一緒に学習計画を立てていきます。また2017年から慶応大学との研究成果を反映させた「AIサポーター」を導入しました。AIが学習開始時や終了時に生徒さんへの声がけや、テキストで対話をします。AI機能はNTTドコモが開発した自動会話プログラムを採用しています。
──社長は2015年に教育再生実行会議の有識者委員に就任しています。eラーニングを活用した教育に国も期待しているということでしょうか。
湯野川 不登校や低学力、経済的な困難といった問題を抱えている子どもを支援する先生をたくさん雇うことは予算上難しいため、eラーニングのようなICTを活用したサポートを充実させるというふうに国の方針も変わっています。
今後は少子化が進行し、教育市場全体はシュリンクしていく可能性がありますが、ICT教育という市場はしばらく伸び続けていくでしょう。エンドユーザーの視点では、子どもに勉強させるための選択肢が塾、家庭教師、通信教育の3つから、eラーニングを含めた4つになったと言えます。
──すると今後は大手が進出してくるのではありませんか。
湯野川 「すらら」のようなインタラクティブなプログラムが入っている仕組みをゼロから作るためには莫大な費用と時間がかかるため大手でも進出は難しいのではないでしょうか。さらに当社には尖ったeラーニングシステムを作る力と、現場の先生方を啓蒙する力があります。その点は強みですね。
子どもが集まる場へのサービスの普及を目指す
── 今後の事業計画を教えてください。
湯野川 学力の向上という実績を元に販売先を拡げていきます。塾については引き続きローカルの大手中堅向けの販売に注力します。BtoCについては、Webマーケティングなどを強化して人件費を抑えて対応します。これまで教育機能を提供していなかったところにも販売していきたい。例えば「放課後等デイサービス」(障がいのある就学児向けの学童保育)、NPO法人が運営する子ども食堂、民間の学童保育などです。
──株主還元についてのお考えを教えてください。
湯野川 現時点では、将来の企業価値を高めることが株主還元につながると考えています。当社は低学力、不登校といった社会が抱える教育問題を本業で解決して収益を上げる新しい企業体を目指しています。ぜひ応援してください。