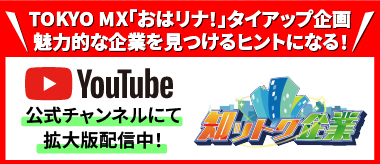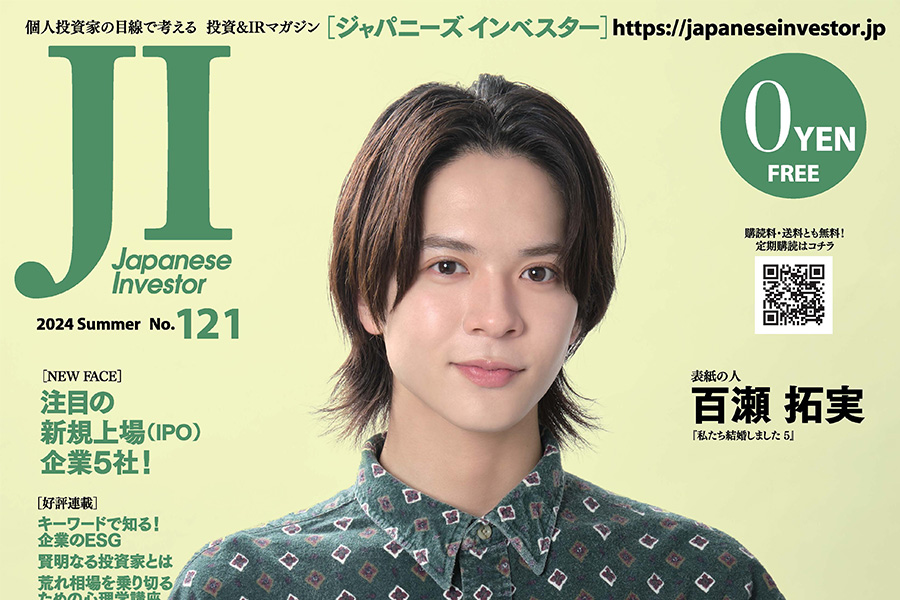ROEは奥が深い指数
かつて、ある精密機械大手の役員とROEについてお話ししたことがあります。その時、その役員は「ROE、ROEと世間は煩いが、なに、こんなの簡単ですよ。借入金を増やせば、ROEが上がりますから」と言い捨てました。ROEを単なる決算技術論に置き換えてしまったその役員と会社に深い失望を感じたことを、私は今でも覚えています。
制度的には自由度の高いフランスでは、50年前に外国人投資家が急増して株式市場の主導権を握るようになりました。ただ、外国人株主の保有比率が高まるにつれ、彼らの要求もエスカレートしてきました。いわく、「フランス企業はガバナンスの程度が低い。もっと株主に情報を与えよ」と激しく迫りました。つまり、大株主の立場で、株主の主張を強めるのはどこの市場でも同じことです。
昨今、日本でもROEについて関心が高まっています。ここでは私のROE論を展開させていただきます。まず、投資家も経営者もいま自身で考えている以上にROEを重視しましょう。なぜ、ROEが大事な指標なのか。その起源を17世紀初頭にさかのぼってみたいと思います。
Rはリターンですから「純利益」を、Eはエクイティですから「自己資本」を意味します。ROEは自己資本の収益力を表しますが、その資本の中には株主資本がどっさり入っています。無論、上場後にため込んだ利益剰余金なども含みます。株主には出資した資本がどのくらいのリターンを生むのか、知る興味も権利もあります。もし世間一般と比べてあまりリターンが低いようだったら、株主をやめようと考えるはずです。
1602年、オランダは東インド会社を設立して南の国との貿易を独占しました。多額の資本を集めて、船や乗組員を調達しました。主として香辛料とか毛皮の貿易を植民地との間で活発に行い、暴利を貪りました。いわゆる重商主義の発展です。ここで史上初めて出資者(資本家)と船長(経営者)が区別されはじめたのです。利害の一致する資本家が集まって史上初めて取締役会を招集したのも当然です。
かくて資本家と経営者は分離して、それぞれの役割を果たすようになりました。現代経営は、資本主義のもと、株主が資金を出資し、会社役員が経営のかじを取るという東インド会社の応用型なのです。そして経営者はガバナンスの徹底を求められ、出資者=投資家はスチュワードシップの実行が必要になってくるのです。
どうして今まで無視されてきたROEがこの数年間で注目を浴びるようになったのか。それは、やはり外国人投資家の勢力(保有高)が強くなったからでしょう。発言力も増してきました。戦後、無条件に借入金を使って設備投資をしてきた日本企業もデフレを経験して、もはや有利な投資案件は見当たらないとばかりにキャッシュをため込んできました。しかし、その流れに変化が出てきたのです。ファナックは1兆円あればこれからの不景気も乗り越えられると「社内にキャッシュを1兆円確保したので、残りの利益は株主に還元する」と今までの行きがかりを180度転回しました。
考えてみれば、成長投資をしないのなら、多額のキャッシュを社内に蓄積しておくのは無駄というものです。株主に還元することによって経営の成功を主張するのも一つの選択肢です。投資家はそういう企業への長期投資を進めるでしょう。かの有名なアメリカの資産家で投資家のウォーレン・バフェットも、自己資本利益率が長期安定している企業に投資するのが正しいと言っています。豊かな自己資本を高いROEで引っ張り上げる。その方程式が当てはまるなら、長期投資は成功したも同然でしょう。よく株式の長期投資を勧奨する個人とか団体がありますが、この視点を取り入れることによって長期投資の理論的な背景が得られることになるのです。
企業のROEは簡単には予測できません。しかし、過去にさかのぼって実績から平均値を出すのがバフェット流です。また、低ROE企業でも、この値が8%を超えると株価が動き始めるという株価の慣行が株式市場にはあるようです。しかし、企業が純利益を増やすということは並大抵のことではできませんが……。

吉野 永之助
よしの・えいのすけ。1936年生まれ。大手外資系投資顧問キャピタルグループの元ファンドマネジャー。